

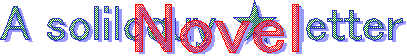
| 舞妓の恋 京都祇園社。 素戔嗚尊、八柱御子の神などを祭る霊験あらたかな神社である。 参拝を終えた後、参拝客は大概南門の鳥居をくぐったすぐ側にある二軒茶屋で一休みをするのが普通であった。軽く白湯をすする人、お弁当をつかう人、軽く京名物の団子をかじる人など、それぞれ思い思いの方法で旅の疲れを癒す。 四条の橋から火が見ゆる 火が一つ見ゆる あれは二軒茶屋の火か、円山の火か そうじゃえ、ええ、そうじゃいな 人混みを縫いながら、今日も又前髪を刺し櫛で整え、後ろ髪を軽く結った若い”おちょぼ”達が客に茶を振る舞う。 「おう。舞坊。今日もいい声で唄ってるじゃねえか」 「あ、おこしやすう。おにいはん」 御茶屋では普通お客さんの事を”おにいさん”と呼ぶことが多い。舞は持っていた茶を客に振る舞った後、盆を脇に抱えて声の元へ駆け寄った。年の頃はまだ三十を少し越えたばかり、材木問屋の若旦那がその声の主であった。 「元気だねえ。おれもお茶をひとつ、つけてくれるかい。あと団子も二串つけてくれ」 「おおきににいさん。じゃもってくるきに」 舞の京都弁は生まれながらの物ではないから、非常にぎこちなさと違和感が抜けない。しかしそれがまた、いじらしくて良いのだと言う常連の旦那衆も多い。 「全く桜屋のおかみさんもお目が高いや。ここの茶屋の娘っ子は皆器量よしと来ているから席に座って茶を飲んでいるだけで本当にいい気分だ」 「おおきに。ゆっくりしてっておくんなせいやし」 桜屋の真ん前には藤屋という茶屋がそびえ立っている。 男の目というのは良く分からないが、皆口を揃えて「桜屋の娘っ子は美人揃いだ」と言う。藤屋の娘達が不美人であると言う意味ではない。桜屋の娘達が突出して綺麗だと言うのである。又更に藤屋においては茶を運ぶ娘達は茶碗を洗ったり、団子を焼いたりと言った下働きもやらされているのに対して、桜屋の娘達は”力のつくような事はせんといていいから”ということで、茶を運ぶ以外、一切の力仕事はしない。力仕事をするのは外部働きに来る男衆だけである。 「それはそうやは。女将さんはわざわざ判人から可愛い子を集めとるんやさかい」 「その噂はやっぱり本当かい」 「そや。うちかて奉公に出される予定と違ったんや。姉さんがうちより先に奉公に出る事になるはずやったのに」 ここまで言って舞は口を止めた。遠くから茶屋のお母さんが目に入ったからである。忘れもしないそれは十歳の冬の出来事であった。 「じゃ、また。ゆっくりしてっておくんなまし」 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 舞の父は川から丹を集めて売る山師であった。 丹とはつまり水銀の事である。丹は染料にも、薬にもなる非常に価値のある物として高く取引される商品であった。 川から川を渡り歩き、浮き沈みの多い暮らしを送っていたある日。弟が誕生した事もあり、ようやく父は一カ所に場所を決めて定住する事を決めた。 「よし、ここで商売を始めよう」 父は京都から少し離れた場所に家を借り、山で取れた鉱石や野菜などを売る商売を始めたのだが、頭を下げた事が無い人間が付け焼き刃の商売を初めても早々上手くいく筈も無く、あっという間に少ないながらもほそぼそと貯め込んでいた貯金を食いつぶした。 そして売る物が無くなったある日。父は忽然と責任を全て捨て、舞達家族の前から姿を消したのであった。 「とうさん・・・」 家族は泣いている場合では無かった。日に日に食べる物は無くなって行き、季節は徐々に秋が終わりを告げようとしていた。 今迄は山から栗を拾ってきたり、芋を掘ったりと何とか飢えを凌いで来たが、これから先は予想がつかない。このままでは家族4人全てが飢え死にしてしまう・・・母が出した結論は早かった。困った貧乏人の家であればどこでもしている事である。 13歳になった姉のまほそを年季奉公に出すことにしたのである。 人づたいに判人を探し、事情を説明する。 人が人を売るのである。そういった商売をする人間は自然と目つきが厳しくなってくる。値踏みされる視線。人見知りをする姉は既に目を背け、母の背中に逃げ隠れてしまった。 「その姉ちゃんの器量だったら10年奉公で30両と言った所かね。それだったら口利き先が無いことも無いけれど・・・料亭の下働きだから、体力的にちょっときついかもしれない。 でも、もしよかったらそっちのちっこい方を奉公に出してみないか。その子の器量だったら倍の60両は出すという京都の茶屋があるけれど。そっちは客に茶を出すだけだから、ちっこいのでも十分やってけると思うけど」 「60両!」 女性の普通の奉公代が年3両の時代にその倍を出すというのだ。心が動かぬはずはない。しかし、まだ舞は10歳・・・一人で見知らぬ土地に出すにはとても勇気がいる事であった。 「京でも有名なお茶屋だから坊の身元は安心だ。どうするね」 母の後ろに隠れている姉と、判人と睨み合う妹。二人の母の結論が出るのは早かった。母は時にはどんな非常な判断をしてでも、家庭を守らなくてはならないのである。 かくして舞は幼くして、京の茶屋に10年間奉公に出ることとなった。 「舞。奉公というのは、その間親子の縁を切ると言う事なんや。くれぐれも茶屋の女将さんの言うことを聞いて、無事年期を終えるまで頑張るんだよ」 「かあちゃん」 京に上がって早三年。正直。田舎の家に居るよりもむしろ京での生活の方が楽であった。桜屋の女将は優しい人であったし、共に働く朋輩の仲間も苦労を知っている者が多く、時にはぶつかる事があっても、最後には分かり合うことが出来る者が多かった。 舞は一度は恨んだ運命に感謝しつつ。桜屋での生活を続けていた。 「あら、大阪のおにいさん。今日もおぼこいお子さんを連れて、ゆっくりしていっておくんなせいやし」 「おぼこいって言うな!年が二歳違うだけじゃないか」 「はいはい。あまーいお団子お持ちしますね」 舞は又京流行の歌を口ずさみ始めた。山育ちの舞の声は誰よりも遠くまで届き、響き渡る。それは客にとって決して不愉快な物では無く、桜屋に来た時の一つの楽しみとなってきていた。 四条の橋から火が見ゆる 火が一つ見ゆる あれは二軒茶屋の火か、円山の火か そうじゃえ、ええ、そうじゃいな (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 京の娯楽の世界は揺れていた。 千九百二十九年。出雲の阿国率いる女衆歌舞伎が風俗上好ましくないと幕府に廃止されてしまったのである。京の夜の街は揺れた。男が女形を演じる若衆歌舞伎なども徐々に始まりつつあったが、それらが祇園の町にやって来る事は無かった。このままでは京の夜の街が消えてしまう・・・危機を感じた桜屋のおかみも寄り合いに参加し、意見を出し合うようになっていた。 「うちは今昼お茶とお菓子しか出して居ないんだけど、旦那さん方からは夜もやって欲しいってよく言われておるんやけど、どないやろ」 「それはええんやないか。でもただお酒を出すだけじゃ、お客は来ないやろ」 「でな、最近醍醐寺の巫女はんだった人が、巫女を降りて、働き先を探しとるって話を聞いたんや。でその巫女はんに夜のお座敷で踊って貰ったらどないやろ」 「それはいい。是非女将さんやりはったら」 桜屋の女将は悪まで”最近思いついたんやけど”という姿勢を崩さなかったが、実の所は数年前から見目良い娘ばかりを集めるだけでなく、娘達に読み書きや舞の稽古をさせ、”御茶屋の新しい形”を模索し、機を狙っていたのだった。 「さて、今日からあの娘たちにもっと頑張ってもらうようにせんと」 桜屋のおかみが帰ったその後ろ姿をじっと見つめている女性の姿があった。それは二軒茶屋のもう一軒。藤屋のおかみさんその人であった。 「またあの腹ぐろ女が何か始めるよ。油断せんと、じーっと見張っておかないとね」 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 「はい。お団子とお薄です」 「ありがとう。舞も京都言葉が上手くなった。びっくりしてしまうよ」 「おにいはん達が喜んでくれますから。頑張っているんどす。ぼっちゃんもすっかり大きくなられて」 「おぼっちゃんて言うな!ぼくには”たろう”という名前がきちんとあるんだから」 「はいはい。太郎ぼっちゃん。坂上のおにいはんも頼もしい跡取りが居て羨ましいどすな」 何気ない会話。このちょっとした会話をしたくて人は桜屋に足を運ぶのである。特にこの大阪から京へ商いに来ている坂上兄は季節毎に足げく、足げく足を運んでくれる。気が付くと日はとっぷりと暮れかかって来ている。そろそろ店じまいの時間である。 「おにいはん申し訳ない。そろそろ店じまいの時間どす」 「わかってるよ。太郎挨拶なさい」 「ふん!」 舞は笑顔で二人を見送る。 店の前の簾を降ろし、桜屋女将の元へ。するとそこには見慣れない、目つき鋭い色白の女性の姿があった。 「皆揃ってるかい。舞で最後だね。 こちら醍醐寺で巫女をされていた姉さんだ。明日からは茶屋を夜も営業する事にしたので、お前達も承知しておくようにしておくれ。 この姉さんは明日からそのお座敷で旦那衆の前で舞を踊って貰う事になっている。お前達も今後はより踊り、歌に精進して、この姉さんの様にお座敷に出られる程の腕前になっておくれ」 「夜も?」 「特にお前達は何もやることは無いよ。 料理は仕出し屋に頼むつもりだし、当面はお座敷には私と、小菊の二人が出るだけになるから。話はそれだけだよ」 小菊と紹介された巫女はニコリともしない。全くの無愛想である。 舞たちおちょぼとは別の部屋に住む事になるらしく、食事も別である。 夜半。光りに誘われて舞は目を覚ました。誰も居ないはずの茶屋の正面の方から薄弱い蝋燭の灯火と鼓の音がするのである。 「はあい。はい」 そうっと覗き込むと。そこには白い衣装に赤い袴を着た小菊の姿があった。 おそらくは巫女の正装なのであろう。桜屋のおかみさんの鼓に合わせて、扇子を振り舞を舞う。それは今まで見たことが無いような静かで、それでいて華のある静かしげな舞であった。 「そこに居るのは誰だい」 みつかった!と逃げようと思ったが、体が動かなかった。ずんずんと大きな足音を立てて小菊が近づいてきた。「えへへ」と笑って逃げようとしたが、小菊はそれを一括し、扇子を持った右手でまいの頬を強く打ち叩いた。 「へらへら遊んでるんじゃない!笑うんだったらここから出てお行き!」 小菊が持っていたのは鉄扇では無い。竹で出来た紙製の扇子である。がしかし、舞の顔には見事にみみずばれの赤い痕が付いた。 とたんに音を聞いて桜屋のおかあさんが駆け寄って来た。 「小菊!ここは醍醐寺とは違うんだから。こんな酷いことは二度と許さないよ。 舞も、もう寝なさい。明日は明日で忙しいんだろ」 「はい。おかみさん・・・」 口の中が切れて痛かった。逃げるように寝室に逃げ帰り、布団を頭からかぶった。 舞を殴りつけたとき、小菊は頬一つ動かさなかった。生まれて初めて感じる完全なる”悪意”であった。「これからどうなるんだろう・・・」見え無いながらもひしひしと感じる恐怖感に襲われ、まいはどうしても寝付くことができなかった。 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 桜屋の夜の営業は大成功であった。 昼間の茶屋の常連さん相手の商売であるが、一晩一人に”はんなり”としたもてなしをするというこの営業は人が人を呼び、予約が殺到したが、桜屋の女将は常連の紹介以外での予約は一切受け付ける事はしなかった。 「一見さんはお断りどす」 目標が出来て、桜屋の朋輩達の稽古も熱が入り始めた。 お客さんの要望で、舞たち半人前も夜にお座敷に呼ばれる機会が増えたのである。 昼の営業と違い、夜のお座敷では貰えるご祝儀の額が全然違う。年季奉公の舞達にとってこうした収入は本当に唯一の現金収入源である。 貰ったご祝儀をおかみさんに取られると思いきや、「おきばりやす」と笑うばかりで取る事は無い。これで、田舎の母さんに仕送りを送ってあげられる。冬にはどてらの一つも新しい物を置くってあげられる。お金さえあれば、当面のかなりの数の夢は買えるのである。 これはもう頑張るしか無い。 「おや、舞。少し痩せたかい」 「坂上のおにいはん。夜の営業が始まってから色々と忙しいのどす。いじめんといってください」 「そうかい。でも向かいの藤屋でも夜の営業を始めるらしいから、少しは時間が取れるようになるかもしれないね」 「ほんまどすか!」 「しかも、桜屋のように一見さんお断りと言うことはないらしいよ」 茶屋の奥から桜屋の女将さんが飛び出してきたが、真意を確認するとまたしても茶屋の奥へと戻ってしまった。何が起こったのかちんぷんかんぷん。桜屋は大騒ぎになるも、向かいの藤屋は至って冷静である。 「一見さんお断りなんて。何て勿体ない。うちらはそうはいたしまへん」 その日から、藤屋では毎晩の様に華やかな宴会が催されるようになった。小菊のような巫女上がりの娘から、若衆歌舞伎上がりのちょっと癖のある芸達者が金襴緞子の衣装を着て座を盛り上げる。手が足りなくなると、茶屋を手伝っていた娘の顔に白い白粉を無理矢理塗り、酒の相手をさせる事もあった。 結果は桜屋以上の大成功であった。桜屋のお座敷には次第に静かになっていくようになった。 「女将はん。一見さんお断りなんてやめはったらええのや」 舞は怒り狂いながら昼の営業を手伝っている。藤屋はとっくに昼の営業を停止させていた。昼ほそぼそと営業するよりも、夜がっぽりと儲けた方が良いという考えなのである。 「でも、白粉を塗ると女って綺麗に見えるのな」 「それは、そやけど」 「まい達も白粉を塗ってお座敷にでてみては?そしたら女将さんだって反対はしないだろう」 「どうやろ」 正直化粧に興味が無いわけでは無かった。 やるなら小手先だけでなく徹底的にやろう。 というのが桜屋の女将の回答であった。 京都一の呉服問屋から金襴繻子の着物と帯を取りそろえ、肌はきめ細かく白粉を塗り混んだ。 勿論お座敷の主役は艶やかな小菊の舞であったが、いつしか舞も週に何日かは座敷に座らせて貰えるようになった。舞の得意の芸は得意の歌である。歌を歌いながら必死に覚えた手習いの舞を舞う。常連の旦那衆は「おぼこい。おぼこい」と舞の芸に代絶賛であった。いつの時代も男性は完成した物ではなく、頼りなげな物の方が好ましく思うようである。 「舞。今日から昼のお茶だし出なくて良いから。夜のお座敷だけになさい」 「女将さん。ほんまどすか」 夜のお座敷で貰える祝儀を溜めた結果、田舎に住む弟を今日の寺子屋に入れることが出来た。弟は寺子屋を出た後蘭学の道に進みたいと言う。これからどれだけお金がかかるか分からない。そういった事を考えると、桜屋の女将の話は正直ありがたい事であった。 「はい。おねがいいたしまっす」 「今日からあんさんはおちょぼやなくて、”舞妓”や。きばっていきんしゃいよ」 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 夜のお座敷はどんどん派手になり、それに合わせてお座敷代ならぬ”花代”も高騰して行った。 夜の京都で時間の経過をしる為の手段は”線香”である。そのお座敷がかかってから、終わるまでの間に何本線香が燃え尽きたかによってお座敷の代金が決まった。無論花代だけでなく、仕出しの食事代や駕籠代など総額は遊び方によってそれぞれ違うのだが、混沌としていたお座敷遊びにも一つの基準が生まれつつあった。 「坂本のおにいはん!」 常連に混じって、昼の部の常連であった坂本兄とその子供太郎の姿があった。二人とも白粉を塗り、高島田を結った舞の姿に動揺しているのが分かる。 「ほら。太郎、舞に会いたかったんだろ。ほら」 ぽーんと。太郎がまいの前に押し出される。どうみても照れてしまっているようである。 「うち、かわいくないどすか。どうどす」 「舞可愛い。でも昼間会えなくなってちょっと寂しくなったかな」 「うちもどす。二人とも来てくれて嬉しいどす」 舞は柔らかく書かれた眉を揺らしてニッコリと笑う。二人ともお酒ではなく相変わらずお茶を飲んでいる。 「太郎が大阪を出て、こっちの寺子屋に通うことになったのでまいにも挨拶しておこうと思って。これから太郎はちょくちょくこっちに顔出す事になると思う」 「そうどすか。桜屋のおかあさんにも言っておきます。おにいはんは大阪に戻られるんどすか」 「そう。そろそろ大阪に腰を据えて商売を始めないといけなくなったのでね」 そこまで話した所で会話は中断された。舞の芸を披露する番になったのである。 「ようーー」 桜屋のおかあさんの威勢の良いかけ声と共に、鼓が鳴らされる。今夜の宴もまた長くなりそうであった。 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 「にくらしい。何だかんだ言って桜屋にはよく客が入る」 藤屋の女将、鈴乃は遠目で桜屋の宴会の火を見つめながら、今日最後の客を見送っていた。折に触れて桜屋の舞妓にちょっかいを出したり、出てきた客を呼び込もうとしたりしたが、なかなかそれは思った様にはいかなかった。 「一見の客は藤屋。なじみは桜屋」 という言葉が出来る程、京都に住む旦那衆は桜屋を好んで利用した。芸舞妓の質はそうは変わらないはず。どこがどう違ってこの差が生まれているのだろうか。鈴乃はその差を自分では見つけられずに居た。 「あないにくらしい茶屋。いっそ燃えてしまはったらええのや そしたら、どないすっきりするやろか」 その言葉を聞いている女が一人居た。藤屋の芸妓、藤花である。 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 「まい!遊びに来たよ!」 「太郎ぼっちゃん!そして朱がねも!」 朱がねは舞の年の離れた弟である。なれた足取りで二人は桜屋の台所へ向かい、残り物の和菓子を受け取って来る。良いと言っていないのにまいの部屋に上がり込み、さっさと扉を閉めてしまった。 「遊びに来るって言ったろ。朱がねも学年は違うけど同じ寺子屋なんだ」 「びっくりしたわ。とにかくおちょぼの誰かにお茶入れて貰うから」 「いいいい。気使わなくて」 とはいえそう言う訳にはいかない。 朱がねは正直、舞の元には来たくなかった様である。年が離れているせいか、嫌いという訳では無いのだろうが、朱がねはあまり舞になついてはくれない。今日も太郎にせっつかれて仕方無くここにやって来た様である。 舞妓になる前の若いおちょぼがお茶を運んでくる。おちょぼ達はこうして礼儀作法を覚え、二年もすれば舞の時と同じように舞を覚え、歌を覚え、一般教養を身につける為に寺子屋へ通う。一般的な肉体労働的な要素の強い”奉公”とは違い、おのおのそれぞれの夢があるせいか、おちょぼ達の目は皆輝いている。希望の多い人間の顔はいつしか澄んでくる物である。桜屋の娘達が皆美人なのは、そうした要素に囲まれているからかもしれない。 「ありがとう。又なにかあったらたのんます」 太郎の手前、そう厳しい事を言う訳にはいかないのだが、茶屋には基本的に男は居ない。女大勢所帯である上に、出雲の阿国の様に風紀が乱れていると幕府に指摘されない為にも、茶屋には男は住まわせない事にしているのである。 桜屋のおかみさんに数年前男の赤ん坊が生まれたが、物心が付いた頃早々に親戚に貰われて行くこととなった。今は、自分の身を守る為には子供だとて犠牲になるのは仕方のない。と考える時代なのである。 「すぐ。帰るって」 と、言ってすぐ帰るはずもなく。どうせ怒られるのであれば・・・と舞も太郎と朱がねの話を聞き入った。以外と桜屋のおかさんは二人の来訪を怒らなかった。 「小さなあぶらむしがふらふら二匹入り込んだ所で、何が出来る年で無し。早く入られたら困るような心配をさせて欲しいぐらいやわ」 馬鹿にされているのに気が付き、舞は不覚にもお座敷で怒りを露わにしそうになってしまう。しかし桜屋のおかあさんの思惑とは別に、舞は年下の太郎に引かれつつあった。何も知らないいいとこのおぼっちゃんの気まぐれ。気まぐれ。本気にしてはいけないのだ。 「舞、遊びに来たぞ。今日は堺から新鮮なふぐが届いたから、厨房の女将に渡してきた」 「ありがと。ふぐ大好きやわ」 太郎も遊びに来るばかりで、それ以上は何も言わない。そんな関係が4年以上続いたであろうか、以外にも二人の関係を変化させるような行動を起こしたのは、大阪に住む太郎の母であった。 太郎が茶屋の舞妓に入れあげている。という噂を聞き、突如として乗り込んできたのである。しかしそのような事情を知らないおちょぼ達は、例外なくいつも通り、見ず知らずの太郎の母をぞんざいに扱い、茶屋の中に入れることはなかった。 「一見さんはお断りどす」 「くやしい・・・」と思う前に、太郎の母は作を練った。 そして、知り合いの問屋の旦那が桜屋の常連であるという噂を聞き、無理矢理一緒に連れていって貰うことにしたのである。 夜。日が暮れ、今日も又桜屋の提灯にも火が入った。 旅の衣装では、と太郎の母もおろし立ての着物に着替え、赤い紅を引いて問屋の旦那と共に茶屋の中に入る。常連と一緒であると対応が大分違うらしい。綺麗な着物とだらり帯を締めた若い舞妓が「おいでやす」「おいでやす」と出迎えてくれる。 「しかし流石女泣かせで知られた坂上の旦那の長男ですな。14歳にして茶屋遊びを覚えていたとは」 「だから心配になって見に来たんでしょう。主人は笑って相手にしてくれないし。こんな時こそ私がしっかりしないと」 客が入った後、芸舞妓が姿を見せた。お客に挨拶をし、茶屋の女将に挨拶をして部屋の中に入る。とたんに宴は始まり、華やかな舞を見せる小菊。美声を響かせる舞の姿がそこにはあった。 「あそこで唄ってはるのが、あんさんが探し取る舞と言う舞妓やよ。この茶屋では小菊の次に人気のある舞妓や」 「あの妓か」 白粉を塗って、顔立ちや表情があまり分からなくなっているとは言え、女の目から見ても確かに舞は美人であった。華やかに歌を唄い、舞を舞う。 太郎の母は見ているだけで何だか腹立たしく、食事も酒も喉を通らなかった。 「どうしたんどす」 「厠はどこ!」 舞が太郎の母の側に来た時、特にせっぱ詰まって居たわけでは無いのだが、不器用にもそう言ってしまった。 舞は近くの舞妓に「お客はん。高野山やって言ってはるから、送ってくるやは」と伝えてから、軽く右手を上げ、太郎の母を先導した。 手入れの行き届いた庭の見える長い廊下を抜け、水の流れる厠へ向かう。このような席になれていない太郎の母は席を立って一対一になったものの、緊張して言葉が出ない。 「こちらどす。どうぞごゆっくり」 太郎の母は後ろも見ず、厠の中に駆け込む。厠を出た後は、もう見る物は見た。もう帰ろうという心づもりであった。手を流水で流し、厠の戸を開ける。すると厠から10尺ほど離れた冷たい床に座り、三つ指をついて太郎の母を待つ舞の姿があった。 「どうしたん、腹でも痛いんか?」 「違います。お客はんが迷子にならんようまっとったんや。何しろ広い御茶屋の事やから」 足に白い足袋をしているとはいえ、この冬空の中。厠の前で客を待つというのは大変な事である。 「何か勘違いしとったんやろか・・・」 帰るつもりであったのが、太郎の母は舞の導かれるままに、座敷に戻ってしまった。楽しい夜は続く。そんな中、太郎の母は大阪を出たときとは違う結論を出しつつあった。 「とはいえ、そうなるというのはお互いが大人になってからでしょ」 翌朝、下宿先で太郎に会うも、昨夜舞に会った事は告げなかった。 「太郎。今好きな人でもいるんか」 「そら居ない事も無いけど、何や急におかあはん」 「おかあはん。やって京言葉で言われるとこそばゆいわ。じゃ、がんばりんさいよ」 そのまま、賄いさんがお茶を出す前にあっという間に立ち去り、大阪へと戻って行ってしまった。 後日舞に太郎の母が座敷に来ていた事を伝えられるのだが、それは太郎が一番びっくりであった。 「どうして分かったんや」 「そっくりやもん。笑いを堪えるのが大変やったわ。何しに来たんやろね」 「それは・・・」 母の残していった意味深な言葉の意味を探る。 「おかあはん。舞と俺が怪しいと思ったらしいぞ」 「勘違いもいいとこやわ。全くもー」 そう言い言葉をごまかそうとした時、太郎は舞の手を取った。 無論太郎はそれ以上するつもりはない。まだお座敷前なので顔に白粉を塗ってはいないので、表情を隠し続ける事ができない。 「俺の事きらいか」 「そら、すきやけど・・・」 二人の初めての意志の疎通。二人の中が接近していくと共に、太郎は舞の部屋の出入りを禁止された。恋をして色気が出るのは芸の助けだが、それ以上は一切お断りと言うことなのであろうか。しかし太郎は桜屋常連の大切な息子である。早々ぞんざいには扱えない。 太郎と桜屋の女将との妥協点を探した結果、入って良いのは入り口入ってすぐの台所までと相成った。 「ま。いいさ。とりあえず上手い物が食べれて、舞の顔が見れるなら」 学業修行中の身が、一人でお座敷に上がるわけにはいかないし、学費以外のお金は大阪の父は送ってはくれない。例え父と共にお座敷で会ったとしても、それは客と舞妓との関係であり、それ以上に進展する事は無い。 それとはなく台所で交わす数行の恋文が二人の愛の証であった。 「しあわせや」 公私共に、舞は絶頂に居た。 「今日は恵比寿神社行ってきたんや。天神さんにお参りして、こま犬に紙をくくりつけてきたんや」 「何でだい舞、こま犬に紙を結んでくると何か良い事があるのかい」 「迷信やいう人も意張るけど、右のこま犬の足には男の人、左のこま犬には女の人の名前の紙をくくると、いつまでも一緒にいられると言う噂があるのをお客はんに昨日聞いたんで、早速行って来たんや。あんさんとの手紙と、名前。若旦那には迷惑やったかな」 「迷惑なんてとんでもない。嬉しいよ舞」 優しく手を握り合う。二人にはこれが精一杯。これ以上を行えば太郎は桜屋に出入りが完全禁止となり、舞の身の上もどうなるか分からない。しかし若い二人にはこれ以上を望む気持ちなど毛頭無かった。 「俺も後で行ってこようかな・・・でもちょっと恥ずかしいかな」 「そな無理せんとってええんや。気持ちだけで嬉しい」 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 芸舞妓とて、日々の修行を怠る事は無い。 そして芸事を本当に極めようと思えば、茶屋に籠もりきって出来ることではない。 小菊、舞を含めた桜屋の面々は定期的に井上流の舞の指南を受けることと相成った。舞は正直気が進まなかった。既に井上流には既に藤屋の芸舞妓が出入りしていたからである。 「おねえはん、だいじょうぶやろか」 「背中をしゃんとして、わては舞のしゃんとしない所が大嫌いや」 小菊が舞の背中を強く叩く。今日はこの痛みが心強い。ざっとお座敷に揃う化粧前の芸舞妓。その中には藤屋の芸妓藤花の姿もあった。 「桜屋も今日は来てはる・・・」 稽古にも小菊は堂々と臨み、流石、京都に桜屋あり、と舞の師匠からは絶賛されていたが、舞はどうしても背中がすくんでしまい、思うように舞う事が出来なかった。何度も稽古をその場所からやり直す。小菊を含めたそれぞれの弟子はそうした本番に弱い舞に対していつも冷たい視線を送っていた。 「もっとしゃんとせえ」 「小菊姉さん。わかっとんやけど」 「あんさんは気が弱すぎるんや。それじゃ人生渡っていけへんよ」 「すみまへん。姉さん」 「あんさん、桜屋の舞妓やろ。ちと話をせんか」 稽古が終わった後、玄関口で舞は藤屋の芸舞妓達四人に呼び止められた。今小菊の姿は側には無い。困った・・・と思う舞を藤花は人の居ない部屋へと舞をずんと連れ込んだ。弱い物を見ると苛めたくなる。それは人であれば仕方のない宿世であるのかもしれない。 「あんさん、桜屋が儲かっているから、調子にのってるのと違うの。稽古は一人が躓くと迷惑なんだよね」 「申し訳ありまへん。申し訳」 「申し訳で済むわけ無いやろ!」 ぬるま湯で育った舞にとってこれが始めての暴力であった。顔はやはり痕が残るからであろうか、帯の隙間や足の股の辺りなど、容赦のない蹴り、拳が入る。泣くものか、泣いてたまるものかと意地を張っても、最後はあまりの痛さに最後は号泣してしまった。痛い。痛い。首、背中、全てが分離してしまいそうだ。 「根性無し。それでも売れっ子舞妓かね」 人の気配がした。占められた襖が開き小菊が姿を現した。 「あんさん達、何やってるの!」 「あらあら、ようやく味方登場かい。私が一番気にくわなかったのは小菊あんただよ!ついでだあんたも」 「やれるものなら、やってみなさい」 小菊は強かった。飛びかかってきた四人を右に左に避けた後は一人づつ、確実に急所に入れ動きを止める。武道は踊りに通じる物があるのだろうか。痛みを堪え小菊の姿を見つめる舞の目には、それは暴力ではなく、何か激しい新しい踊りを踊っているように見えた。 「あんた化け物?」 一番最後に藤花の顔に大きな青タンを作り、小菊は動きを止めた。舞は駆け寄りたいが体が動かない。あまりにも殴られ過ぎた為、むち打ちになってしまった様である。 「次に私の妹分をこんな事にしたら、顔だけで済むと思わない方がいいわ」 「おのれ小菊!この恨み、晴らさずにおかぬべきか」 「何もできない芸妓の分際で。偉そうに言うんじゃないわよ」 「できない?本当にそう思うのかい?」 切れた。藤花は何か頭に思いついたのか、ケラケラ笑いを浮かべて床に伏してしまった。逃げるなら今の内、小菊は舞の立つのを片手で手伝い、部屋を後にした。 「小菊!あんただけは一生許さないよ!覚えておき!」 どうやら藤花にとっても、これが始めて受けた暴力であったらしい。藤花の受けた傷は一ヶ月以上消えず、消えた後も光りの角度によっては小さな痕として残ってしまうこととなった。お座敷では白粉を塗るため、お客やおかみさんに気がつかれる事は無いが、一人部屋に入り蜂蜜入りの石鹸で白粉を浮かした後、冷たい流水で洗い流すと、その屈辱の痕はいつ、どんな時でも消えること無くその場所に現れた。 「この恨み、晴らさずにおかぬべきか」 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 何の前置きも無く、突如桜屋が炎に包まれた。 火を殆ど使わない茶屋が一体何故・・・という疑問を持つ前に、飛び火を防ぐために、どんどん桜屋が打ち壊されて行った。 家が倒れると確かにその部分の火の勢いが弱まって行った。舞達に出来ることは出来るだけ多くの衣装と小道具をそこから運び出す事だけであった。 自分たちの荷物は燃やしても、これだけは燃やせない。箱が破れ金襴錦が道路に投げ飛ばされた。汚れた物は洗えばいい。でも消え去ってしまったらもうお仕舞いなのである。 「みんな無事かい。小菊。舞、あやの・・・」 荷物が一通り運び終わったのを確認してから桜屋の女将は点呼を取った。皆、煤まみれの顔をしているが、何とか無事であるようである。 「大丈夫。皆が無事でさえあればいくらでも桜屋は再興出来る。あたしに任しておきんさい」 「女将はん・・・」 その言葉通り、燃え落ちた次の日にはススけた材木が取り払われ、地ならしが始まった。再興は出来る。元の様に営業できるんだ。と作業を見つめる藤の前で、藤屋は桜屋の火事以前より以上に、にぎやかに営業を続けていた。 「舞妓は手が汚れるような事をしてはあかん」 と言われ、気持ちがせっても、結局出来ることと言えば舞の稽古だけである。 数ヶ月後、建物は無事元の姿に改築されたが、そこには多額の借金が残り、家は戻れど、桜屋は正に廃業の危機に直面していた。 その頃からであろうか、藤屋の横暴が目に見えて酷くなってきたのは。 再建途中においても多少の嫌がらせ、営業妨害があったのだが、最近の物は度を超してしまっている。 「とっととやめちまいな」「うっとおしいねえ」など、罵声をかけ、家の中に猫の死体やお湯を投げ込んで行く。しかし又迂闊に手を出し、再建途中のものが崩れ去ってしまっては大変である。我慢。我慢。我慢。朋輩達にもストレスが見え始めてきていた。 時間が過ぎるにつれ、桜屋一の芸妓小菊も精神的に耐えきれなくなり、贔屓の民宿の旦那の妾として桜屋を引退すると言い始めた。 ”桜屋が危ない”火事の危機を皆の力で乗り切ろうとしている時に、櫛の歯が一本一本折れるように、何か大切な物が気が付かぬ内に姿を消しつつあった。 最後のお座敷が終わった後、小菊は始めてまいの部屋の前に立った。 「ちょっとよろしおすか」 「ねえさん」 しゃなりと冷えた床に敷かれた煎餅座布団の上に座る。元々小菊は奉公で桜屋に居た訳ではない。次に住むところさえ決まれば長居をする理由などどこにも無いのである。 「今日からあんたが桜屋を引っ張っていかんと。後頼めるな」 「ねえさん」 「いつか、あたしの気持ちが分かる日が来ると思う。あたしは桜屋をずっと一人で引っ張ってきた。あたしが風邪で倒れたら桜屋は終わりやったんや。だから稽古とお座敷以外頭の中に入らんかった。それであんさんに冷たい思いをさせたかもしれん」 「ねえさん。それはわかっとうから」 小菊はうっすらと涙を浮かべていた。初めての出会いから既に5年が経過。涙はおろか、小菊が人前で感情を露わにする所を見るのも舞にとっては初めての事であった。 「またいつかここに戻ってくる。それまで頼めるな」 「はい。ねえさん」 「舞、お前にだけ教えるけれど、実はこの体にはややこが宿っておるんや。ここに長居して流産でもしたら大変な事。ややこがこの体を離れ、舞えるようになったら又ここに戻ってくる」 「ややこが・・・」 詳しく話を聞けば、相手は今回の落籍先の民宿の旦那であるという。旦那の家は跡継ぎに恵まれず、どうしても小菊の腹に居る子供が跡継ぎとして欲しいのだとどうしても説得されてしまったのだと言う。 多少の嫌がらせなどには負けない根性は持っている。しかし女として生まれた以上、せめて一度くらいは子供を産んでみたい。小菊の中では苦肉の判断であった。 「旦那も桜屋の再建費用については出来るだけ面倒を見るといってくらはる。数年の我慢や。がんばって うちらの後ろにはまだまだ小さいおちょぼが居る。舞妓が居る。うちら二人が何とか桜屋の提灯を灯し続けなければあかんのや」 小菊はそこまで言うと、涙を堪えきれなくなったのか、席を立った。恨む恨まぬという話では無い。この時になって初めて、舞は小菊の偉大さに気が付いた。 正直、好きではなく、むしろ嫌いであり、時には舞妓同士で群れて小菊の悪口を言った事もあった。が、しかし、実の所小菊は黙って舞妓の盾となり、場を盛り上げ、桜屋を成功させて行った立て役者。その小菊がこの桜屋に明日から本当に居なくなってしまうのである。 「舞、お願いがあるんやけど」 舞の年季奉公は来年で終わりである。 いくら辛くても、来年まで我慢すれば田舎に帰ることも、大阪の坂上の家に入る事も出来るのである。久しぶりに稽古の汗を流しながら、舞は母屋へ向かった。 「舞、お前の面倒を見たいという旦那さんが居るんやけど、どうやろ」 「どうやろって・・・面倒を見るってどういう事やの」 「一晩だけ、お前の旦那さんになりたいって事なんやけど。ほしたらこの茶屋の再建費用全部出してくれはるって言うんや。舞、最後のお願いや、この話受けてくれへんやろか」 舞は桜屋の女将の顔が見えず、声も出なかった。 桜屋の女将は舞の前に両手で三つ指を付き、深々と額が床に付くほど頭を下げた。 お客さんのお出迎えでもこれ程頭を下げることは無い。「頭を上げて下さい」とまいが声をかける前に、桜屋のおかあさんは言葉を続けた。 「向こうさんは全て知ってはる。お前は目を閉じて大人しうしていればいいんや。すまん。すまんのは分かっとんのやけど、これしか手がも無いんや」 「私は太郎はんのお嫁はんに・・・」 なりたいんや。けど、 と続けたかったが、この年季奉公の十年間の恩を忘れる事は出来なかった。あの桜屋のおかあはんが頭を下げている。私などにあの誇り高いおかあはんが頭を下げている・・・ どんな手段を使っても、桜屋の提灯を消すわけにはいかない。 「女将はん。頼むなんて水くさい。分かってます。店のため、女将はんの為です」 「では、承知して・・・」 「はい・・・一晩だけ・・・どす」 見ずの人と床を交わす。それは処女である舞が一つ大人になる事を意味していた。 一月後、桜屋は元の通り、完全なる姿で再建された。 檜の臭い漂う廊下を、寝室へと続く廊下を一人裾を引きずりながら歩くまいの姿があった。太郎との楽しかった日々が頭に浮かんだ。 と、廊下の戸が突如開き、汗まみれになった太郎が姿を現した。どうやら誰かが余計なお節介をしたようである。息を切らせながら太郎は、「どうして、どうして」と呟いている。 「ごめんなさい・・・」 「舞、お前は俺の嫁になるんやろ。どうしてこんな事を・・・」 「許して。あたしはこの桜屋を見捨てることはどうしても出来ないんや」 「舞、俺を捨てないでくれ・・・恵比寿神社のこま犬に誓ってくれたんだろ・・・」 舞の後ろに控えていた男衆があっという間に飛び出して来、太郎を取り押さえた。乱れた前髪を直し、まいは一夜旦那の待つ寝室へと向かった。 恋の終わり、新しい人生の始まり。舞は涙を流すことなく襖の戸を開き、しずしずと中へ入って行った。 「楽しい夢を見たと思おう。所詮私には叶わぬ身分違いの恋でした」と頭の中で思い、白い布団に静かに体を横たえる。 後に舞妓の衿替えの儀式を”水揚げ”と呼ぶようになるが、それは少し未来の話である。 「どうぞ宜しくお願い致しやす」 その夜、白い寝室から薄い虹色ウスバカゲロウが飛び立って行くのを見た人が居たとか、居ないとか。舞は翌年衿替えをし、芸妓として独り立ちをした。 太郎は桜屋を去った後、荷物をまとめる事も無く即大阪に戻り、数年京都へ戻る事はなかったと言う。 舞妓の恋が一つ終わったのである。 四条の橋から火が見ゆる 火が一つ見ゆる あれは二軒茶屋の火か、円山の火か そうじゃえ、ええ、そうじゃいな |
| コ |
