

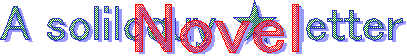
| 科挙夢粋演技 三千年の雄大な歴史を持つ中国大陸において、三大奇習と呼ばれる日本に全く伝わる事が無かった習慣があった事をご存知だろうか。簡単に代名詞だけ上げると”宦官”、”纏足”、”科挙”がそれにあたる。これらの習慣は中国と言う国を理解して行く上で重要な役割を担っていたと言っても言い過ぎでは無いと思う。 女王卑弥呼の時代に一部伝わったともされる宮刑とも腐刑とも呼ばれた男性器を取り去る宦官制度。取り去られた男性器は死に至った時まで大切に保存され、棺桶に一緒に埋葬されるのが通例であると言う。文字通り死して元に戻ると言う事だが、こうした生物繁栄の根本的原理に逆らう自虐的な習慣は日本に根付く事は無かった。 女性の足に包帯を巻き理想の形に整形を行う纏足。これは女性の逃亡防止及び理想の体型を作成する為に行われた。足が小さい纏足をした女性は常に下半身に負担がかかる為骨盤が広くなり、出産に適し女性器も鍛えられ非常に具合が良かったと言うのだ。金瓶梅と言う中国の古典文学においても女性は全身裸になっていても足だけは靴を脱がなかったと書かれているから、女性の足に対する関心度と言うのは現代と同じく非常に高かったのでは無いかと言える。無論こうした美意識に対する関心度と言うのは民族毎に違い日本人には腱の通った健康的な足の方が魅力的であったようだ。実際日本の歴史上には纏足をして活躍した女性の名前は一人として残っては居ない。 上記二つはある意味特権階級の人間の為だけの習慣であったのに対し、最後の一つ科挙だけは試験に受かりさえすれば誰でも高級官僚になる事が出来ると言う全国民男子に関係した習慣であった。日本にも鎌倉時代一部伝わったと言う記録も残っているが、日本の政治は常に特権階級の中にあり長くは続かなかった様だ。農民は農民。士農工商という身分制度が成立した事も考えるとある日突然貧乏人が金持ちになると言った出来事は親が子供に読み聞かせる物語の中でしか存在し得なかったのかもしれない。 殷・周・秦・漢・魏呉蜀・南北・隋・唐・宋・元・明・清 科挙制度は具体的な年代で言うと五九八年隋の時代に官僚制度の一つとして始まり、中国王朝時代最後清の時代に複雑怪奇に完成される。元々は貴族に政治を乗っ取られた皇帝が自分の為に働く新しい部下が欲しかった。と言う事に端を発する様であるが、当初読み書きが出来れば合格。方言が直っていれば合格。と非常に簡単な試験であった物が気がつけば文体・内容共に”科挙文化”となぞられるほど複雑怪奇に出来上がり、完成されて行く。 科挙合格者「生員」にあらずんば人にあらず。そんな言葉が生まれたのは”清”の時代であると言う。科挙制度が最盛期を迎えて居たこの時代。「人生変る試験」中国独自の文化として大成された科挙文化は様々な人間の人生を変え、操って行く事となる。 ---------------------------------------------------------------------- 中国・天津郊外。 田舎の朝は早い。 儒教の教えを忠実に守る流星の家では男子は婦女子の誰よりも早く朝食を済ませ、早々に勉学の準備へと入るのが普通であった。本日の朝食は玉蜀黍を引いた粉で作ったマントウに香草の湯が少々。食べ盛りである兄弟達の満腹にはとても足りない量であるが、文句を言う者はは誰も居ない。父は遠く北京で官僚をして居るが、北京では何かと物入りらしく仕送りは無に等しい。母・祖母を含めた家族八人の生計を支えているのは国立学校の校長をしている皺の寄った祖父の手一つなのである。文句など言をう物なら罰が当たる。 「ごちそうさま」 長男である流星は祖父が食べ終わるのを見計らい、揃って隣接する国立学校へと向かう。流星はまだ十七歳であるが、既に国立学校への第一入学資格である県試に合格していた。次男・三男は独学の為揃って日当たりの良い学習室へと向かう。「県試に合格し、塾へ祖父と向かう」二人にとってそれは確実に実現しなければならない夢の一つであった。遊び盛りの子供達にとって自由になるのは夕方のほんの一時しか無い。 「流星!」 一日の勉学を終えようやく自由時間。共同井戸で顔を洗っている流星の元に近所に住む幼馴染の亜香がやって来た。家は決して貧乏と言う訳では無いのだが、纏足をしていない。その理由は亜香の姉が三歳の頃纏足をした為に、運悪く足が根元から腐り死んでしまうと言う事故が発生したからである。 纏足の方法としては、最初横巻きにして足を細長くし、次に縦に巻き、第二指以下を足の裏側へ折り曲げて先のとがった菱形に整えるのが普通である。その手法は家によって違い名人が行う纏足の手法は門外不出とされ、単純に折り曲げると言った物理的な方法論だけでは語り尽くす事が出来ない。 その後足の形が安定した五歳以降は纏足用の靴を履き足の形を整える。足の形が完成する前に死亡すると言うのは決して珍しい事では無いのだが、長女の死を心底嘆いた亜香の父は続いて生まれてきた娘達に纏足をする事を諦めた。 宋代の頃は纏足をしなければ嫁に行かれないとも言われたが、現皇帝咸豊帝の寵妃である懿貴妃も纏足はしていないと言う。北京からは「旗人は足を縛ってはならぬ、漢人は縛り布を解け」と纏足を禁じる法令が届いていた。しかし纏足をしなければ娘は嫁に行けないと信じる人も多く、嫌がる娘の足を縛り続ける親の数はそう簡単に減る事は無かった。 「県試に受かった感想はどう? 却って忙しくなったのかな?」 「責任感を感じるようになった。父が当てにならぬ事もあるし、とにかく我が家は俺が守らないと」 「そうそう。今日慌てて来たのは他でも無いのだけど悪い噂を聞いたのよ」 「又どうせ大した事無いのだろ?」 笑いながら弁髪の先端部分を背中に投げ首にぐるぐると巻きつける。元々弁髪は戦争が多かった時代、首を敵から守る為に伸ばし纏めるようになった習慣であると言うが、今は漢人成人誰しも自然に伸ばし編む髪形であった。弁髪の先から水滴がぽたぽたと地面を塗らす。流星は「やはり濡らしてしまったか」と片手で水滴を軽く絞った。屈託の無い笑顔は無論県試に受かったとて変る物では無かった。 「あ、又ばかにして! 聞いてびっくりしないでよ。これはそのあんたの父親の事なのに」 「父が? 何かあったのか?」 年に数度しか会う事の無い父の事は、残念ながら今の流星にとってどうでも良い事となっていた。元々父は後継ぎに恵まれなかった陳家の養子であり、最初の繋がりからして縁が薄かったと言うのは仕方の無い事ではあるのだが…… 「噂だけどね。噂。どうやら北京で再婚したって言うのだけど?」 「再婚?」 あり得ない話ではある。顔の汗を拭き取り、流星は言葉を濁した。今の時代男にとって離婚は非常に簡単な手段だ。つまり七去と呼ばれる ・父母(舅姑)に従順でない事、 ・子のない事 ・多言な事 ・窃盗する事 ・淫乱な事 ・嫉妬する事 ・悪疾のある事 のどれか一つにでも該当していれば、第三者の手を借りる事無く「お前を離婚する」と妻に言い伝えるだけで離婚が成立してしまうのだ。しかし妻側にも三不去と呼ばれる権利があり、 ・帰る実家の無い事 ・舅姑の三年の喪を果した場合 ・夫が貧賤の時嫁して今は富貴になった場合 の三点いずれかに該当した場合離婚を拒否する権利が発生するのだ。流星の母は家持の娘であるし、後の二つにもどう考えても該当しない。しかし父と母は元々離れて暮らしている訳だから今更離婚の必要性などあり得るのだろうか? 「結構これって重要な話じゃない? 何かあんたは聞いてないの?」 「いや何も」 「本当の所が分かったら最初に私に教えてね! 私はあなたの未来の奥さんなのだから!」 言いたい事を言うと、人目を憚らず両手を流星の広い背中に回しべったりとまとわりついて来た。膨らみ始めた胸の感触が微妙に伝わって来る。「やめろよ」と一応嫌がる振りはするが流星とて決して悪い気はしない。醜女ならともかく亜香はほっそりと白く伸びた手足に眉月のように整えられた眉、澄んだ湖のような瞳を持ち、決して欲目では無く村一番の美女と言っても言い過ぎでは無い容貌を誇っていたからだ。 基本的に自由恋愛はどこであっても禁止されては居たが、流星と亜香の場合は運良く家柄的にも釣り合いが取れており、回りの人間も「長じれば似合いの夫婦となろう」と二人の、ある意味玩具遊びのような恋愛を見守っていた。現在の二人の行状を一々咎める者は誰も居なかった。 「父が再婚??? ま、今更と言う気もするが、良くここまで持ったものだと言っていいのだろうか」 亜香と別れ自家へと向かう。暮れかかった太陽を斜めに見つめながら、さて母には何と言って聞こうかと一応愁傷考えてしまう。男にとって離婚はある意味簡単な出来事であるが、女にとっては一生を左右する大事件であるに違いないからだ。 草深い門を抜け母屋へ。もしかしたら既に夕餉を作りに廚に出向いているかもしれないが……と思った先に母の姿があった。祖父と一緒に何やら話し込んで居た。 「母上!」 遠目に見えた時点で声をかける。二人の会話が止まった事が目にも分かる。ばつ悪そうに思いはするが、高まる好奇心には勝てずついつい小走りに走り寄ってしまった。辿り付いた後は着衣の乱れを直し、慇懃に祖父に一礼をした後で母に一礼をする。 「亜香に聞いたのですが、父上が再婚された、とか」 何も考えず単刀直入に聞いてしまった……多少の後悔はしつつも、合わせて祖父の眉がつっと動く。余計な手間が省けて良かったと言うべきか、母はごくりと唾を飲み中年太りの腹の前に手を重ねた。 「いえ、それは違います。父上は北京にて亡くなられました。先月の事です。運悪くあなたの県試の時期と重なりましたので私一人が北京に出向き葬儀を済ませました」 そう言われてみれば先月母は曖昧な理由で供も少なく北京へと出かけていたような気がする。忙しくてあまり気には止めていなかったのだけれど…… 「父上が亡くなられた、と」 「遺体は本人の遺志により父の遺族へと渡しました。残念ですが、こちらの墓には入らないとの事です」 いくら縁が薄かったとは言え父が死んで驚かない子はそう居ないだろう。呆然と言葉を失う流星。母は姿勢を崩さずに言葉を続けた。 「しかし父上はあなたを、多くの兄弟達を残してくれました。お陰で祖先の線香の火を絶やさずに済みます。これからはあなたが中心となって、この家を支えていって下さい。半年後は府試も控えています。心を乱す事無く母を助け頑張って下さい」 「はい」 返事をするのが精一杯。母と祖父はその後会話を続けるでも無くそのままその場を立ち去ってしまった。離婚なら良い、と言う意味では無いが既に死んでいたとはとりあえず驚きの事であった。心を乱してはならない。母の言う通り半年後には府試があり、その後続いて院試が控えて居るのだ。ここまで受かってやっと祖父が校長を務める国立学校に入学が許可されるのである。今は回りの人間が「県試に受かった」「受かった」とのんきに盛り上がっているので特に説明する事はしていないが、実際毎日流星が学校でやっている事と言えば、祖父の書童として墨を擦り、書籍を用意すると言った事が中心なのである。祖父が授業に出ている合間に勉強をしていると言うのが現状で、決して授業に出席して居る訳では無いのである。 「皆勝手な事ばかり言って、次の府試で更に半分が落とされ、院試で半分が落とされてしまうんだぞ……」 一般に科挙試験と呼ばれる試験を受けるには、国立学校の生徒である事が第一の条件とされる。がしかし、今の日本でもそうであるように学校に入学をするには入学試験を通過しなくては成らないのだ。そうした物が県試・府試・院試である。どれか一つ受かれば良いと言うものではなく、下から一つづつ、合格して行かなければ次の段階に進む事は出来ない。国立学校に通う資格を得る為、金持ちは自宅に家庭教師を雇い私塾を開き対策を練るのだが、そうで無い者は独学で四書五経をまず丸暗記する事から始める。最終試験にまで合格する者は一万人に一人とも言われる。 「そっか。流星のお父さん亡くなっちゃったんだ。どこで離婚って変ったんだろう?」 「知らん。しかしまあ母はもう結構いい年で体型で再婚の意思も無いようであるし、生活が変る事は無いだろう」 「形だけではあっても一家の大黒柱が居る。居ないと言うのは大きな違いがあるけれど」 「そうか?」 亜香の言う事はあてずっぽうではあったが、長い目で見ると確かに当たっては居たのだ。父は祖父の経営する国立学校唯一の最終試験・朝考の合格者であったのだ。それが縁で母と結ばれる事となったのだが、科挙合格者が居ない国立学校程情けないものは無い。同じ国立学校だった。と言う縁で将来持ち上げてくれる先輩が居ないと言うだけでなく、「この学校で本当に受かるのか?」と言った疑問さえ浮かんでくる。かくして一人減り・二人減り祖父の国立学校の生徒の数は櫛の歯がかけて折れていくかのように減り始めていた。生徒の数が減れば収入も減る。かくして夕食の内容も日々少しづつより粗食へと変貌を遂げて行った。 「他を見るな。自分を信じて行け」 「はい」 「お前なら出来る。いややらねばならんのだ」 気を散らしてはならない。一度失敗すれば次の試験は三年後である。何度受ける事が可能であるとは言え、人間の時間には限界がある。流星は必死で勉強を続け府試・院試に連続して合格をした。祖父の国立学校に入学し、生員と呼ばれる資格を会得したのである。これは科挙に挑戦する人間にとって最低条件となる事であった。 こうトントン拍子に進んで行くと回りの空気は大分変ってくる。来年は本格的な本当の意味での初科挙試験となる卿試もあり、今の調子で行けば合格は間違い無いだろう。気がつけば流星十九歳、対する亜香も十七歳の適齢期となっていた。「そろそろ……」そんな声が亜香の家族から上がって来た矢先の出来事であった。 「結婚ですか?」 相変わらず一心不乱に机に向かう流星の元に祖母と母がやって来た。手にはその相手と思われる絵姿を持っていた。亜香? と思い絵姿を受け取り中野女性を眺めるとどう見ても外見がまるで違う。絵に描かれていたその女性の足は綺麗に纏足され、糸のように細い眉を持ち明らかに亜香とは違う容貌をしていた。 「これはどちらの方ですか?」 「北京の豪商柊さんの四女・鈴と言う方じゃ。お前もそろそろ結婚しても良い年だろう」 「しかし、私には……」 「亜香の事ですね」 母は冷たい面持ちでパタンと流星から受け取った絵姿を下に置いた。有無を言わさぬ雰囲気を漂わせ、流れるように言葉を続けた。 「第二夫人と言う事であれば反対はしません。あれはあれいい娘だと思います。しかし正妻は鈴と言う事は必ず了承して貰います」 実は流星と亜香は既に体を交わしている。二人の関係が壊れた場合損害を受けるのは一方的に亜香の方である。純潔では無い女性の嫁入り先などろくな所が無く場合によってはそれだけの理由で離縁される事も少なくは無い。純潔を失い嫁入り先を失った娘の唯一の抗議方法。それは一人黙って首を釣る事である。そうした命をかけた抗議をして初めて純潔を奪い逃げた男性が世間的に非難される事になるのである。それ以外逃げた男性が非難される言われは無い。 「流星。この茶器をごらん。どこの世の中に急須が一つ、茶碗が一つと言う茶器があるかい」 「しかし。私は」 「返事は今すぐで無くて構わない。が、しかしこれはもう決めた事だから」 部屋の空気が一瞬にして凍る。ぽとんと手にしていた筆が紙の上に落ち、黒い染みを作った。瞬きをする事さえも憚れる。祖母と母は絵姿を伏せたまま、すっと机の上に置き部屋を立ち去って行った。科挙を受けるという事は儒学の徒となる事である。そうした場合両親に逆らう事は教え上許される事では無い。流星に今求められた決断は単なる嫁取りの問題だけでなく、今後の将来をも決定する重要事項であった。 「亜香……」 流れ落ちそうになる涙を堪え、目を閉じ、嗚咽を右手で押さえる。選ばなくてはいけない道はどう考えても決まっている。その後何をして、道をどう歩いていたのか覚えてはいなかった。気がつくといつもの水場に亜香と二人立ち尽くして居た。気を使ったのか回りには誰も居ない。流星が結婚すると言う話は既に亜香の耳に届いていたようである。太陽は既に落ち始め、太陽のその日最後の赤い光が二人の顔を照らし続けていた。 「結婚。するんだ」 単刀直入に言葉を濁す訳でも強める訳でもなく亜香は流星の返事も待たず質問を続けた。気持ち的には流星は亜香になじって欲しかった。自分の不甲斐無さを貶して怒鳴り散らして欲しかった。 「家お金無いもんね。これから出世したいなら仕方ない事だよね」 「兄弟多いし、親の言う事は絶対だもんね」 「私と結婚しても、はっきり言っていい事って余り無いのよね」 「傷物の娘はどうしたらいいんでしょう。教えてよ。頭いいんでしょ」 「やっぱり女は纏足していないとお嫁に行かれないのかなー。やっぱり辛くてもやっておけば良かったのかも。今更言っても遅いけどさ」 淡々とした語り口で亜香は語りながらその場に膝を抱えて座り込んだ。逃れられない運命。今流星が学んでいる学問によれば、黙ってこの場を立ち去る事が一番の正解であった。いっ時の気の迷いで大勢を見失ってはならない。自分の中では良く分かっている筈の事だった。亜香もそれを望んで居る事が汲み取れた。それとなく背後に人の気配を感じる。何人もの人間が二人の経緯を沈黙の中見守っている事は明白な事であった。迂闊な行動は流星の人生をも左右する事に成りかねないのだ。 「さよならは言わないで、これ以上私を苛めないで」 「亜香……」 してはいけない事。自分の人生を今までの苦労を全て棒に振る事。全てが分かって居た。流星は流れる涙を隠さず下を向く亜香を抱きしめた。「すまない」とも「やはりお前と結婚したい」とも口に出して言う事が出来なかった。自分の力の無さ、不甲斐なさが身に染みて辛かった。力が欲しい。でもその力を得る為には今出来る事はこれが精一杯であった。 「泣かないでよ。一番辛いのは私なんだから。大好きだよ。あなたが一番大切。他は何も要らない。だから許してね」 数日後、その後恨みを言いに来るでもなく亜香は井戸に身を投げ、若い命を絶った。遺書は無く、近所の人間も流星にその不実さをなじるような事はしなかった。亜香は女二人で一人の男を分け合う事を潔しとしなかったのだ。その死に顔を見て人々はそう判断した。 卿試を半年後に控え、しめやかに流星の婚儀が執り行われた。鈴は亜香とは全く正反対の性格で、流星の言う事をいつも静かに聞き、笑顔で「そうですね」とただ答えるような大人しい性格であった。北京の豪商と縁を結んだ事は確かに流星の家に幸福をもたらした。食事の内容が良くなった事は勿論の事、家が増築され、国立学校の施設もどんどん充実されて行った。独学を強いられてきた兄弟達の勉学についても一人一人に家庭教師が付けられ、より充実した教育を受けられるようになって来た。 「後は流星が卿試に受かれば、言う事も無し」 卿試の前に行われる合格率一/百の予備試験である科試にも流星は無事合格した。次の卿試に受かれば任官する事さえも可能である。実際祖父もこの卿試まで合格し任官していた過去がある。夏の暑い盛り、八月に故郷を離れ、流星は試験会場となる北京へと向かった。試験は長丁場となる為妻子を伴って行く人間も多いが、流星は「一人で大丈夫」と伴の下男を一人・下女を一人連れただけであった。試験が行われるのは八月九日であり、その前日に必要最低限の荷物を持ち、試験会場となる貢院に入る事となる。 「久しぶりの北京だが、変ってないなあ」 幼い頃父に会う為に母と通った道。泊まり慣れた旅籠に宿を取り、気持ちを落ち着かせる。試験会場入場の当日。試験会場で使用する土鍋・食料品・布団・すずり・墨などを持って試験会場へと向かう。門の前では故郷から祖父が流星の本人確認を行う為に待っていた。これは試験の代理受験を防ぐ為で、今年祖父の国立学校で卿試を受けるのは流星だけであるから、流星の本人確認の為だけにワザワザ出て来た事になる。 「本人です。間違いありません」 再会を喜ぶ事無く確認が済んだ後は身体検査が行われる。不正を徹底して禁止する為である。確認をする試験官の方も発見した場合は銀三両を報酬として受け取る事がで切るので、下着の中、持ち込んだ食料の中まで徹底して調査を行う。 「よし。入って良し。三三三五番の房に入れ!」 渡された紙と房の番号だけを頼りに自分の入るべき場所を探す。荷物が重い上に試験会場は膨大に広いのでこれだけでひと騒ぎである。流星もようやく自分の番号の房を見つけ、荷物を中にしまいこんだ。 「試験の時は甘い物が殊に体に良いと言います。どうぞお持ちください」 黒い袋の中に目に付いた赤い缶の中に仕舞われた鈴お手製の甘い砂糖菓子を何気なく口にする。この暑い季節に表面の砂糖部分は半分溶けかかっていたが、鈴の言った通り普段食べなれない甘い物もこの時はとても美味しく感じた。硯・筆と共に机の上に食べかけの缶を置く。試験の合間に食べ、万が一解答用紙を汚してしまってはいけないのだが、何やら置いているだけで心の支えとなるような気がした。 「閉門!」 受験者が全て房に納まった事を確認して、試験会場の大門が閉められた。これで試験が終了する十五日まで何があっても開けられる事は無い。持参した布団に包まり流星は眠りにつこうとしたその時である。房にかけたカーテンがごつい男の手で無言に開かれ、どこかで見たような顔が覗かれた。故郷からは自分以外の人間は受験していない筈なのに…… 「流星。久しぶりだな。父の顔をもう忘れたか」 男はカーテンを閉め中に入ってきた。隣の房に聞こえぬよう低い小さな声である。父? 流星はがばっと布団から身を起した。 「父上? 母は死んだと」 「残念ながら足は付いている。丹花には離婚の旨連絡したが、察するにお前には死んだと伝えたのかもしれん。ま、どちらでも結果は同じだが」 悪びれる節も無い。見れば服は試験管の服を着ている。科挙試験の試験官はかつての科挙合格者が行うと言う話は聞いていたが、まさかここで父に再び会おうとは! 「門でじいさんの姿が見えたので、もしかしたらと思い受験者名簿を覗いてみたらお前の名前があったのでな。まあ遠からぬ縁もある訳だし顔ぐらい見せておこうかと」 「今どちらにいらっしゃるのですか?」 「俺? 俺か。北京を離れ地方の知事として赴任している。細かい事は知らない方がお互い幸せだと思うが、知りたいか?」 「そうですか」 「もしこれからお前が科挙試験に進み続け、もし最終試験まで進んだなら又会う事もあるだろう。その時はお前の力になってやる。と、言うよりもお前が俺の力になってくれ」 流星は返事をしなかった。かつて父であった男は言いたいだけ、言うとそのまま房を出て行った。心が乱れる。亜香が言っていたように、やはり父は生きていた。衝撃に一人思い悩みそうであったが、明日以降の試験を考え再び布団に戻った。父が生きていようと、いまいと俺のこれからの人生には何の変更も無い。再び目を閉じようとしたその時、目の前に赤い服を着た人影が見えた。 「父上? まだ何か用事が?」 人影が首を振る。カーテンは閉まったままである。寝たまま薄明かりに目を凝らし正体を探る。水がぽたんぽたんと床に落ちる音が聞こえる。髪は乱れて長い。もしや! 「亜香!」 寂しそうに頷くように首を傾げる。貢院には幽霊が出ると聞いた事があるがまさか本当に出るとは! 流星はまたしても身を起し、凝視した。 「俺が恨めしいのか。名残が尽きないのか」 「そう。あなたも恨めしいが、あなたと結婚したあの女も憎い」 「どうして死を選んだ。何故もう少し待ってくれなかったのか」 「それは嘘。家を守る事を第一に考えるあなたが私と結婚できる筈が無いのだから」 「俺を連れに来たのか、お前の今住む世界に」 人影は寂しく微笑んだ。ぽたぽたと水の音だけが床に染みて行く。 「あなたが恨めしい。そしてあなたを縛り付けているこの科挙と言う試験が恨めしい。私はまだ成仏できないでいるのにあなたは……」 冷たい人影の手が流星の首に伸びてきた。流星は抗う事をしなかった。ここで殺されるのなら仕方が無い。と 「共に黄泉路までと約束した。亜香お前に殺されるのなら構わない」 「馬鹿な人。そして愛しい人。あなたは私よりも宦官に囲まれ纏足の嫁を持つ朝人としての栄誉を求めた。人としての最大の栄光を求めて」 翌朝。流星は人の声と太陽の光で目が覚めた。慌てて全身を確認する。何も無い。夢だったのか。厭な夢を見た…… と布団をたたみ床を見て顔色が変った。寝る前は乾いていた床の土が何故か水でびっしょり濡れていたのである。 「亜香やはり昨日来たのか!」 思い悩む時間など無く、試験は始った。四書題三・詩題一について草稿紙に十分案を練る。試験内容は多岐に渡り、一週間受験生は房にカンズメにされる事となる。試験が終了するのは八月十五日。合格発表は翌月九月五日から二十五日の間に行われる事になる。合格者は百人に一人である。 「流星!」 試験を終え、弱った体を鼓舞し試験会場を抜けると祖父の姿が目に映った。後ろには旅籠に居るはずの下男の姿も見える。 「迎えに来たぞ。荷物を早くこちらに渡せ」 疲れている流星を促し、祖父は大通りに向かって指を指した。どうやら既に旅籠を引き払い別に宅を借りている様である。 「どうだ、手ごたえは」 「書けたとは思いますが、しかしこればかりは結果が出てみないと」 いつもは言葉が少ない祖父が饒舌に語りかけて来る。もう卿試に受かったかのような口調である。 「今日は仲秋の名月じゃ。鈴の実家の方で酒宴を開くと言うのでな。そちらの方に世話になっている。鈴も昨日から北京に来てお前の帰りを待っている。寂しがっているから今日位は優しい言葉でもかけてやってくれ」 既に酒が入っていたのか。考えてみれば妻の鈴の実家はこの北京にあるのである。暑い日ざしを色白い顔面に受けながら流星は試験会場であった出来事を話し始めた。 「貢院におばけが出るという話は本当だったのですね」 「おばけ?」 「笑ってください。父上のおばけと亜香のおばけが出ました。二人とも言いたいだけ、好きなように言って出て行ってしまいました。全く酷い話ですよね。試験を頑張れなら分かるのですが、私の気持ちなど何も聞いてはくれませんでした」 「父のおばけが出た?」 祖父の顔を探るように見る。酔いが一気に覚めたようで「そんな筈は無い。あれはまだ生きている」と言わんばかりの顔つきである。 「ええ。過去はどうあれ二人はもう私には関係の無い人物です。いや関係があってはいけないのです。私が今守るべき者ではありません」 祖父には暗に全てを知っていると言う事を伝えたかった。程なくして大きな門構えの家が見えてきた。言うまでも無く鈴の実家である。流星は言葉を止め、祖父の先導を待った。 「おーい。婿殿を連れて戻ったぞー。開門!」 祖父もそれ以上この件には触れなかった。その夜は雲一つ無い闇夜に丸い美しい仲秋の名月が踊る。流星も数年ぶりに酒を口にした。久しぶりと言う事もあり酔いの回るのは殊の外早かったが、楽しかった。 一ヵ月後、流星の元に卿試受験失敗の旨の連絡が入った。次の受験は三年後。次こそは。それは亜香を失った流星が一番分かっている事であった。 [完] |
