

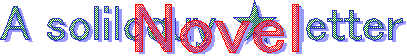
| 蘆溝橋 汗ばむ八月。俺は日本を飛び出して中国・北京へとやって来ていた。 北京の夏は暑い。そうは聞いていたのだが、実際は日本よりも湿度が低く、俺にとってはむしろ過ごし易い陽気であった。一応建前上は交換留学生である為、到着当日は大学の留学生楼へと腰を落ち着ける。前払いした宿泊料は一泊米アメリカドルで八ドル程度、日本円にして約千円程の値段だと思う。その値段を考えると趣味の悪いピンク色のシーツに鉄パイプのベッドでも多少仕方ないなと言う気分になって来る。授業が始まるのは三日後からである。それまでは、個人が自由に動き回る事が出きるようになっているのである。 「おしっ。やるぞ!」 と気合だけ入るものの、結局到着したその日は、何もせず本当にそのまま寝てしまった。日本から中国までの行程は地図上では左程の距離は無いのだが、直線コースでは北朝鮮の上空を通らなくてはならなくなってしまう為、航路は直線ではなく歪曲した遠回りとなっている。航空運賃をケチって中国系の航空会社にした事も身体が疲れてきってしまった理由の一つだろか。翌日目が覚めた時は既に昼の時刻を大幅に通り越してしまっていた。 慌てて水道で顔を洗い、髪型を整える。喉も渇いていたが、硬水である水を飲んで酷い下痢をしてしまう可能性があるので、手間ではあるが、一階の雑貨屋で水のペットボトルを買った。五百cc入っていて値段は三元。安いのか高いのか。今はそれすら分からない。水は無味無臭で、味らしい味も無い普通の水である。とりあえず目的地への出発は明日にする事に決め、校内を歩き回る。 中国の大学は日本の大学と違い、独立性を維持する為町としての機能を形成している事が多い。大学の中に先生が住み、病院、レストラン、散髪所、が併設されるのだ。大学生と言うだけでこうした施設に無条件に入れてくれる懐の深さを感じもしたが、外国人である事が分かった瞬間、品物の値段は二倍から三倍に跳ね上がる。理由としては中国人は既に税金としてこれれら施設の運営費を支払っているのだから、支払っていない外国人は多くお金を払って当然である。と言う理由のようなのだが、俺も大人しく大枚を支払う気は無かった。適当にマントウとコーラを買い部屋へと戻ろうと留学生楼へと足を向けると、途中ベンチに座っていた中国人の女の子に声をかけられた。 「あなたは日本人ですか?」 流暢な日本語である。俺は驚きながらも軽くうなずいた。中国でナンパ? 「私は高校で日本語の勉強をしています。もし宜しかったら友達になってくれませんか?」 「そ、それは構わないが」 彼女の名前はチャンと言うのだと言う。誘われるままベンチの前に立ち話を聞いた。言葉は日本語だが顔つきは化粧気の無い中国人の物である。鼻の下には髭と思しき産毛が薄く生えている。中国人は結婚するまで鼻の下の産毛を剃らないと聞いた事があるが、どうやら本当の事であるようである。大した事では無いのだと思うのだが、目線が丁度鼻の辺りで止まってしまった。 「そうですか。今月一杯中国に居るんですね」 「明日はちょっと訳があって、蘆溝橋へ行ってみようと思っているんだが」 「蘆溝橋。シシの橋ですね。私も一緒に行きましょうか? 大丈夫ですか? 一人でバスを乗って行く事出来ますか?」 「いやその。多分大丈夫だと」 「明日何時ですか? 留学生楼の前で待ってますよ」 この子は蘆溝橋の意味を知っているのだろうか? 知っていて一緒に行きたいと言っているのだろうか? 俺はその点についてどうしても気になってしまい、簡単に寝付く事が出来なかった。 「まさかなあ。知らないなんて事は無いよな」 翌朝は晴れだった。昨日と同じようにまず水道へと向かう。まだ誰も起きていない様である。ジャーと水道の口を開くと中から赤い水が流れてきた。「うわ」と声を上げるが、五分もしない内に透明な水へと戻って行った。昨日の夜からの水が滞留していたのだろうか、「交換しろよ」と言いつつ簡単に身支度を整えた。今日はついに蘆溝橋を目指すのである。 「さ、行くか」 出かける前に昨日と同じ水を雑貨屋で購入する。チャンは帽子を被って約束どおり外国人楼の前のベンチに座って待っていた。チャンの指示に従いバスを乗り継ぎ只管目的地を目指す。中国のバスは乗った後行き先を告げ中で切符を買うのが普通である。丁度バスの中央部分辺りにおばさんが立っていて「切符を買え」「切符を買え」と煩い事この上ない。良く分からないのでとりあえず札をおばさんに渡すと、薄汚れた人民元とバスの切符が手元へと戻って来た。 押し合いへし合いのバスを降りた後は歩きである。川沿いをひたすら歩きつづけた先に目的地があった。目的地の名前は蘆溝橋。現地の人たちには”虎の橋”と親しまれ、かのマルコポーロがその美しさを欧州に紹介した事から”マルコポーロ橋”と呼んだ有名な橋である。橋の袂には乾隆帝の「蘆溝暁月」の碑があり、閲覧料として二元が徴収された。 「何でもかんでも商売だな」 チャンがボディガードとなって、後を追いかけて来る物売りを追い払ってくれた。中国語で怒鳴りつける姿は日本語を話している時とは全然違う顔つきである。チャンは来年大学を受験し医者になるつもりだと言う。母親が薬剤師で父親が大学の先生なので、大学に小さい頃から住んでいるのだと言う。話をしていても分かるが、学識レベルは相当高いようである。 「こっち、これがシシの橋ね」 「結構でかいんだなあ」 感慨にふける間も無く、橋の上を歩く。橋の入り口と出口の部分は小物売りの屋台が並べられ、観光客相手の商売をしていた。とりあえず客引きの手をかいくぐりながら橋の中央部分を目指す。そう俺はついに目的地に到達したのである。 日本人にとっての蘆溝橋はマルコポーロも乾隆帝も関係無い。高校の教科書にはオマケ程度にこの橋の由来が書かれていたが、日中戦争勃発の地なのである。一体一体表情を変える虎の置物には今もまた銃弾の痕や薄くなった血糊が残っていた。指で触って感覚を確かめる。想像していた時よりも実感が湧いては来たが、中国人に対する謝罪の念は沸いては来なかった。 「チャン。この橋で何が起こったか知っているか?」 「知らない。何かあったの?」 「昔日本と中国の戦争が、この橋から始まったと言われているんだ」 「それは知らない。そうなのか?」 チャンは無邪気に顔を横にする。日本人であっても蘆溝橋と言われて意味を知っている人はごくごくわずかであろう。俺の場合は日中戦争勃発時じいちゃんが駐留軍として北京側のこの蘆溝橋側に駐屯していた事が縁の始まりである。当時中国と日本は条約により南満州鉄道の沿線については、一キロ当たり何人という駐兵の条件を結んでいた。じいちゃんはそうした中・開戦を体験し、敗戦後家族を連れて日本へと戻った。現在その時置き去りにされた日本人の”残留孤児”問題が取りざたされているが、俺だってどこかで運が変われば同じ立場であったかもしれないのである。他人事では決して無い。 じいちゃんは死ぬ直前に良くこういっていた。一生に一度で構わない。蘆溝橋を訪れてあの時の非礼を詫びてくれと。ぼけたじいちゃんの戯言と言ってしまえばそれまでなのだが、俺は今・何故か約束を守り、この地に立っていた。 「あそこでワシは生まれて初めて人を殺した。あの時の感触が未だに忘れられん」 じいちゃんはそう呪文のように呟いては、右手の人差し指を曲げ銃を撃つ素振りをする。蘆溝橋の戦闘の際じいちゃんは片足を負傷し、早々に日本に家族共々送致される事となり、病院で治療を受けている内に終戦を迎える事となる。唯一の戦闘経験がどうしても記憶から消え去らない。それ程強烈な場所であるのか、と思ったが、どちらかと言うと川は静かに流れ、岸では乗馬体験なども行われており平和そのものの様子を呈していた。 「次行ってみるか」 蘆溝橋の側に抗戦館と呼ばれる日中戦争の記念館が建設されていた。入場料は留学生であれば五元である。金を支払い中へと入る。そこは橋で感じた感覚とは全く異質の戦争と言う恐ろしい物に対するモニュメントの数々が並んでいた。 蝋人形による日中戦争再現映画。その時の新聞記事。本当にこれを同じ日本人がやったのかと思うと全身から怒りが湧き上がってきた。その当時日本は宣戦布告を行わなかった為通常の戦争と扱いが違うと判断し、捕虜に対して交戦法規を適用せず、「俘虜は全部戦闘中なるを以て之を射殺せり」と容赦無く捕虜を全滅させた。中国側の建物である為、表現が中国人寄りであるのは仕方の無い事であるが、建物を出た後は一体何と言っていいのか分からない状態であった。 「悲惨だ。こんなに酷いとは思わなかった」 俺は中国にやって来た事を多少後悔していた。もうすぐバスの最終時刻である。留学生としてこの国にやって来た以上、大学へと戻り授業を受ける義務があった。 「さ、行こうバスが来るよ」 「チャン。すまない。すまない……」 腰に吊るしていた水を取り出し飲もうとする。中の水はポチャンと音を立てるばかりでもう大して量は残っていなかった。「私の飲むか」とチャンは腕の鞄の中から茶葉と水が入った瓶を取り出した。茶葉は完全に開き、水は茶色い。これを飲めと言うのだろうか? 「ジャスミン茶。落ち着くよ」 恐る恐る瓶の白い蓋を開け、口へと流し込む。ほわっと優しい花の香りがした後喉に優しく生暖かい茶が流れていく。決して厭な味では無い。礼を言い、チャンに瓶を返す。チャンは大切そうに瓶を鞄の中に仕舞い込んだ。 「昔の事は知らない。でも大切なのはこれからだから」 「これから?」 「そう。中国と日本の国が仲良くなる事。過去を後悔するよりもそれが一番大事なことだとチャンは思う。泣かないで。チャンは何とも思っていないよ。中国人ちょっと大げさな所あるから」 その後どうやって留学生楼へと戻ってきたのか良くは覚えていない。覚えているのは「さようなら」と手を上げたチャンのティーシャツの下からのぞいた脇から黒い大量の腋毛が覗いていた事だけである。中国人は剃らないと言う噂を聞いてはいたが、まさか本当だったとは。頭の中がぐるぐるぐるぐる。俺は一体何が出きるのだろう。 答えはまだ見つからない。でも今、俺は何か出来そうな気がしてきていた。 [完] |
