

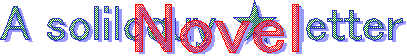
| 釆女の恋 大宝元年、大宝律令が制定され日本において中央集権制度が確立された。天皇を中心とし、一つの国家として日本は成立した。政治は勿論の事、文化、人間さえも全て都に集められた時代。大を生かすために容赦なく小を殺した時代。そんな時代地方から物品の献上と共に人が贈られるという習慣が続けられていた。 「さて、桜様そろそろ行きましょう。名残惜しいのは分かりますが、そろそろ立たないと夕刻までに従兄弟君の所に着かなくなってしまいます」 「分かっています。まだ思い切れなくて」 贈られた人間は決して卑しい奴隷といった種類の人間では無い。身分は郡の少領以上の姉妹又は子女で、年は十三歳以上三十歳以下の容姿端麗の処女に限ると言った厳しい条件が付けられていた。主として天皇の御簾の内に勤務し、生涯独身を過ごすことが基本であった。地方の人間が都へと続く事の出来る唯一の道。いつしかその職は切り捨てられた側の人間にとっては憧れとなり、奉仕を希望する人間が増えて行くようになった。 「さあ、もう駕籠に乗って下さい」 「分かりました」 その職の名前は釆女と言った。増え続けた釆女に対し政府は釆女にも男子の下級官吏に倣って定期的に休暇を与える事を決定した。十年以上前に離れた故郷など既に忘れてしまっている状態。自由を与えられた釆女達は戸惑いを隠せないでいた。 桜はしぶしぶと用意された駕籠に乗る。駕籠の前には牛が従者二人に抑えられ出発の時を待っている。その後ろには桜の侍女二人を乗せた駕籠が用意されている。駕籠にかけられた御簾から離れるかつての住まいを覗き込む。門の隙間からは荷物が片づけられた伽藍が見えてきた。始めてこの屋敷に入ったのは数え年十三歳の時であった。姫・姫ともてはやされた田舎とは違い、都での生活は窮屈極まり無かったが、刺激も多く楽しかった。一生この地で全てを終える。つもりであったのに何故このような事になってしまったのであろうか。後ろから再び侍女のアヤメが桜の元へとやって来た。桜よりも十歳以上年輩のアヤメは心配性である。 「では出発致します。お疲れになりましたら前の下男にご連絡を。出立」 アヤメの声を合図に、行列は動き始めた。駕籠二ヶ、下男三人、護衛十人程の小さな行列である。動き出した事を確認して、やむ無く御簾を下げ中央に釣られた体を支える為の紅白の紐を手に取った。桜の故郷は山を越えた遙か陸奥の国の方角である。戻るとは言ってもそう簡単に戻れる距離に故郷は無いのであった。 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 「桜戻ったか!長の勤めご苦労であった」 「父上!お久しぶりでございます」 頭を下げ久しぶりに会う父に挨拶をする。頭の白髪が増えたか、と思うが目は幼い頃と同じく鋭く輝き、肌は相変わらず野を駆け回っているせいなのか、黒く焼け年齢よりも若く見える。桜は釆女の正装として、唐風の上着に裾の長い裳を引き、髪は両頬に垂れさせてから上部で二つの輪を乗せ束ねていた。下には長く引きずる緋色の袴を着、絵衣には椿をあしらっていた。地方には絶対に無い神々しい桜の姿にに、いつも付いている従者はともかく、田舎の屋敷中の人間は度肝を抜かれていた。 「美しく育ったな。父は嬉しいぞ」 「ありがとうございます」 太陽の光を殆ど浴びずに過ごす桜の肌は誰よりも白い。口にあしらった紅色が更にその肌の色を際だたせている。父に促されて屋敷の中を案内される。幼い頃の記憶とは全く違う屋敷の構造。父の部屋、そして母の部屋を廻り、屋敷の入り口近くにある宴会場へと案内された。 「今日はお前が戻ってきた記念の宴だ。大いに楽しんでくれ」 「ありがとうございます」 今まで給仕する立場であったものが、急にされる立場になると混乱してしまう。我先にと酒の入った素焼きの瓶を持って集まって来る。父は桜を一番上席に座らせ、皆にこう紹介した。 「長く都に勤めに出ていた長女の桜だ。美しく成長して戻ってきた。今日は桜の無事を祝って飲んでくれ」 「乾杯!」 陽気に杯を交わす人々。宮廷での静かな宴会とは全く違った光景である。桜は笑顔で酒の追加を断り、静かに座り「はい」「はい」と返事をするだけに終始するようにした。集まってくる人の数が多すぎる。とても名前を覚えられる数では無い。 「疲れた・・・」 宴たけなわになって来た為、桜は父に軽く会釈をして中座した。宴会場を抜けて長く続く廊下の先に小さなあずま屋が見えた。草履を履き中庭を横断してあずまやへと向かう。小さい頃には無かった物である。あずまやの前には小さな池があり、色の黒い恋が悠然と泳いでいた。 「都の風雅とは又違うけれど、面白いかもしれないわね」 あずまやに用意されていた椅子に座りぼんやりと池を眺める。後で聞く所によると、ここは父の自慢の場所であるらしく、父の許可の無い物は座る事はおろか近づく事も許されていないのだと言う。人々はあずまやの木枠の隙間から見える桜の美しい姿を垣間見ながら宴を続けていた。 「お疲れですか」 誰?と両手に持たれかけていた頭を上げると目の前には父と同じく色の黒い一人の若い男が立っていた。笑顔から覗く歯の色は白く、あずまやの戸にかけた両の手の先は猟で使い込んでいる為か傷だらけであった。流石に中に入る事は躊躇っている様だが、他の人間とは違う何か特権階級独特の臭いがした。 「始めまして。スズカと言います。お父上に私のことはお聞きになられましたか?」 「いえ何も。何分、今日着いたばかりですので・・・」 男性とこれほど近く、面と向かって話した事など無い。桜は恥ずかしくなって顔を斜めにして表情を隠そうとしたが、御簾の無いあずまやの事である。髪が乱れて頬にかかるばかりで全く効果は無かった。 「あなたが都に立った後も、先もあなたのお父上には残念ながら男子の子は産まれる事はありませんでした。跡継ぎの無いことに困ったお父上は私を養子に立てられたのです」 「養子に、でございますか」 「年齢的にはあなた様の弟になります」 「弟!」 妹が四人程産まれたという話は風の便りに聞いていたが、まさか弟まで居たとは。少領ながらも国を統べる父からすれば当然の事であるのであろうが、新しい人間関係の誕生に桜は目を丸くするばかりで次の言葉が出てこなかった。 「あなた様には不愉快な事であるかもしれませんが、都からお戻りになっている間、出来る限り居心地良く過ごすことが出来ますよう努力する所存であります。お困りの事がありましたら是非ご相談下さい。これから宜しくお願い致します」 「は、はあ」 一礼するとスズカは立ち去って行った。桜はとたんに気が抜けて再び両肘をついて池に向かって頬を向けた。こんな所に一月も居なくてはならないのか・・・都に居たままの方が良かったかもしれない。結局その日桜は宴が終わるまであずまやで過ごしていた。ぽーっと飛び回る蜻蛉を目で追い、居なくなると池の中の鯉に焦点を合わせる。誰も桜を咎める物は居なかった。突然舞い降りた美しい鳥。桜は自分の存在の重大さを全く気がついては居なかった。 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 翌朝 「桜、昨夜はご苦労だったな。あずまやは余程気に入った様だが」 「ありがとうございます」 「改めて我が一族を見ると、女が多いな」 父と共に朝食の膳を囲む。場には桜を上座にスズカ、そして四人の姉妹、正妻である桜の母、妾と続く。この時代妾であるからといって身分が低いという事は無い。多少の身分差はあっても母子共にほぼ同様の権利を有する事が出来るのである。 「今日はお前に会いたいという客人が来ることになっている。宜しく頼むぞ」 「私にですか?」 都から戻ったばかりの桜に会いたいという人物。それは一体誰なのだろうか、上座に父と共に座り客人を待つ。暫くすると数人の従者に囲まれた一人の中年男性が入ってきた。知らない人間である。一体どの様な用件なのだろうか・・・ 「釆女様にはご機嫌麗しう。初めてお目にかかります」 「うねめさま?」 通常釆女は自分の産まれた土地の名前で呼ばれる。桜は宮廷に置いては本名ではなく、生まれた土地、陸奥の釆女と呼ばれるのである。間違っても様付きで呼ばれる様な事は少なくても宮中ではあり得ない。 「今日は釆女様に是非朝廷でのお話でもお聞きできればと思いやって来ました。こちらはささやかでは御座いますが貢ぎ物で御座います。どうぞお納め下さい」 「はあ」 後ろの従者が金で作られた首飾りを箱に入れてやって来、桜の前にそれを置いて下がった。何か勘違いをしている。そう思いはしたが隣で嬉しそうに笑みを浮かべる父の姿を見るとそうとも言えなかった。適当に相づちを打ち、相手をあしらう。このような地方に住んで朝廷での勢力図など全く関係ないであろうに、朝廷の有力者や天皇の性状などについて話すと、客は目を丸くして喜び、満足していた。 「都からお戻りになってお疲れの様子。又訪問させて頂きます」 ようやく席を立った。これで終わり・・・と席を立とうとした桜の前に入れ替わりで新しい客がやって来た。父が桜を手で制し、座るよう目で促す。前の客と同じく貢ぎ物を桜に渡し、朝廷の話を聞きたがる。繰り返し。その日一日で十人以上の客がやって来たであろうか、桜はほとほと疲れてしまった。 「父上。これは一体どういう事なのですか?私は朝廷に戻っても何の権力も権限も無いのですよ。あのように多大な期待をかけられては迷惑です」 「そう言うな。この辺りの国で釆女を出しているのはうちだけだ。皆お前が羨ましいのだよ。せめてこの国に戻ってきている間は彼らの相手をするのもお前の重要な仕事だよ」 嘘だ。 父の目はそう言っては居なかった。今父の目は権力への欲望に燃えている。具体的な物は分からなかったが、桜を餌にして何らかの行動を起こそうとしているのは間違いが無かった。 「あ、それからあずまやが気に入った様だな。うむうむ。あそこはお前の為の場所にしようじゃないか。自由に使って貰って構わない。他の家族は使わないよう言っておこうじゃないか。明日も又頼むぞ」 「明日も?」 いそいそと目の前に並べられた貢ぎ物を当たり前のように片づけるよう指示する父。これらの貢ぎ物は桜にでは無く父に用意された物なのだろうか。 「疲れた・・・」 特に行くところも無いので、釆女の衣装のままあずまやで体を横たえる。目を閉じると耳には池の静かなさざ波の音が聞こえてきた。遠くからは鳥の鳴き声も聞こえる。国に居る間だけの、せめてもの親孝行と思うべきなのであろうか。色々と余計なことを考えていると、地面からドン・ドンという規則正しい足音が聞こえてきた。 「お休みですか」 足音の主はスズカだった。木製の水の入った桶を手に持ち、外から中を覗き込んで来た。桜は慌てて乱れた髪を掻き上げ、足を整えその場に座った。 「いや、ちょっと疲れただけ。何か用事でも」 「回りの川で面白い物が取れたので、喜ぶかと思って持ってきたのだが、ちょっと見て貰えないか?」 「面白い物?」 興味を引かれ、スズカの元に歩み寄る。差し出された桶の中には水が入れられ、一匹の赤い魚が泳いでいた。大きさは桜の手の平程で尻尾の先は少し白く、目は数珠程の大きさで丸かった。口に髭は無いので鮒であるのかもしれないが、魚の体型的にはがっしりとしていて、鮒よりもむしろ鯉に近いような気がした。 「これは?赤い魚など今まで見たことが無い」 「鯉なのか鮒なのか、私にも分かりませんが数日前から川に姿を現すようになりまして、本日ようやく捕まえる事が出来ました。病気を持っているかもしれないので、池に離すのは数日後になりますが、喜んで頂けますか」 「これを私に?」 「池に放して、是非ご鑑賞下さい。田舎の事で何も楽しいことは無いかもしれませんが」 「ありがとう」 何だかその時はその言葉が素直に出た。 その時の桜にとっては、その赤い魚は目の前に虚しく並べられる金銀財宝よりも価値があった。数日後池に入れられたその魚は稗をこねた餌に全く近寄らないばかりか、池に桜が近づくとあっという間にその姿を消してしまう。仕方なくあずまやに戻りぼんやりと池を眺めると、時間をおいてすっと池の表面部分へ姿を現し、残った餌をついばんでいる。他の先住の鯉たちはその赤い魚を決して苛めようとはしない、むしろ怖がっているようであった。 「お気に召しましたか?」 突然目の前にスズカが現れた。慌てて乱れた裾を直し、顔を上げる。以後は父に頼んでスズカもこの場所に来ないように頼もう。と思いつつ、軽く会釈をして、書きかけ途中の手紙の方へと向かった。スズカも別に用事があって来たわけでは無い様だがその場を離れようとはしない。視線を気にしつつも筆を取り、紙に書を続ける。目線が筆の先を追って居るのが分かる。人に手紙の内容を読まれて気分が良いはずもなく、桜はしばらくして筆を置き、スズカの方へ声をかけた。 「人の手紙を横から読むというのは良い習慣では無いと思いますが」 「気にしないで下さい」 「気にします。用が無いのであればどこかへ立ち去って下さい」 「内容を読まれていると心配されているのであれば、その心配は無用です。私は字が読めませんから」 「字が読めない?」 「私の気持ちの中では美しい絵を見ているような感じです。内容については一切分かりませんので、安心して下さい。私の悪口を書いている訳では無いですよね」 笑顔で誤魔化す。この時代地方での識字率は殆ど無いに等しい。字が読めるのは神殿の巫女や読むことを職業とする書記官のみである。一番上に立つ長ですら字が書けない読めないという事は珍しい事では無いのである。それを桜は知らなかった。 「え、でも心配ないです。ここでは都と違い字が書ける書けないと言うことはあまり大きな問題ではありませんので」 「でも・・・」 読めれば楽しい。書ければもっと楽しいのに。と言葉を続けたかったが、深刻そうな顔になってしまったスズカにそんな事を言うことは出来なかった。暫く場の空気が凍り付いていたのだが、用も無いし、とスズカが立ち去ろうとした事により桜が動いた。 「折角ですから、こちらに戻っている間だけでも字を教えましょうか?」 「字を?」 「そう長いことここに居られる訳ではありませんが、次のこの国を背負って立つ人間はやはり今後字が書けないと困ることが生まれると思います。どうでしょうか」 「本当にですか、教えて頂けるのですか」 「私に出来ることであれば」 桜は国に戻って来て、初めて自分のすべきことを見つけたような気がした。 都から戻った釆女が字を教えている。噂は千里を駆け巡った。とたん近隣の長の子供達が桜の住む屋敷へと通ってきた。ある者は従者と共に近くの屋敷を借り住み着くようになった。大騒ぎになってしまった。父はというと反対するどころか、一番大きな宴会場を勉強の場として与え、必要であれば高価な紙も筆も用意してくれた。桜は既に釆女の衣装を脱ぎ、普通の着物を着て生活を続けていたのだが、その姿はあきらかに普通の女人とは違う物であった。いつまでも抜けるような白い肌に、知性の籠もった澄んだ瞳。すんなりと背中まで伸びた髪はあくまでも艶やかで体の動きと共に、流れるように左右へと優しく揺れる。 「あずまやで書いていた文章、あれは何だったのですか?」 平仮名を大分覚えたスズカがある日桜にこう聞いた。共に勉強をするようになってから、むしろ個人的な会話は少なくなってきたが、その分親密度は上がってきたような気がした。かなり桜の生活に突っ込んだ質問をしてくるのである。 「同じ釆女の友達に手紙を」 「手紙?」 「文字が書けると折々の自分の気持ちを書きつづって、相手に伝えることが出来るのです。私も都に戻ったら、スズカ、あなたに手紙を書くようにします」 「私も書けるよう、いらっしゃる間必死に勉強させて頂きます」 都へと戻る日は大分近づいて来ている。別れは近いのである。 「私はいずれ都へと戻ります。でもすぐに帰ってきます。待っていてくれますか」 「それは・・・」 二人は静かに目を見合わせる。釆女の恋は今始まったばかりなのである。 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 桜の手紙は山を越え、遠く若狭の国まで届いていた。 桜と同じく休暇を貰い国へと戻ってきていた珊瑚は手紙を受け取り、部屋で内容を読みふける。珊瑚の年齢は二十五歳、釆女としてはかなり年輩な方である。容貌はは都で磨かれ輝くばかりであるのだが、不格好に下半身には膨らみがあった。桜のようにお上からの指示で田舎で休暇を取る者も居れば、珊瑚の様に止むに止まれぬ事情で休暇を取る物も居る。釆女は処女である事が条件であるが、諸事情により処女で無くなる者も居る。一番よい例がお上のお手つきとなり、寵姫となる事だが、それ以外にお上以外の男性と秘密の恋の相手となる場合がある。この場合発覚した場合は釆女はお役目御免、即刻帰国となり、相手の男子は降給や最悪の場合は島流しといった罰則が待っている。道ならぬ恋の甘美な誘惑は時として悲劇の最後を生んでしまう。 日々男子と接触を持つことのない単調な生活。そんな中で潤いを求めてしまうのはそんなにいけないことであろうか。というのが珊瑚の考え方である。結果望まぬ妊娠をしてしまった珊瑚は堕胎を望みつつも、果たせず結果実家へと戻ってきて居た。用意されたのは広い庭のある大きな館である。珊瑚はこの館に数人の下人以外立ち入る事を禁止した。妊娠の事実が漏れない為にも門の外に着けられた警備は厳重である。外界から隔離された空間。そんな中での珊瑚の楽しみは折々に送られてくる手紙や物語、そして代理人によって届けられる貢ぎ物の数々であった。 「陸奥の釆女は元気でやっているようね、予定通り都に戻る、と。戻ったら物語絵巻を送るように言っておかないと」 手紙には赤色の魚の絵が添えられていた。つまらない。持ってきた絵巻は全て読んでしまった。珊瑚は自由にならない自分の躰に苛立ちを感じていた。初めての妊娠、初めての出産である。父は喜んで居るのだが、十月十日が終わるまで動けない自分の身を恨めしく思った。手紙を読み終わったので今度は届けられた荷物を一つづつ手に取り、中身を確かめる。朝採られたばかりの花束から始まり、金糸で織られた反物、陶器が続く。都の趣味の物に比べ何と不細工な物か、と呆れる珊瑚がいつも楽しみにしている荷物があった。その荷物はどの荷物よりも小さく、隅に置かれているのが普通であった。 笑顔で手漉き和紙にくるまれた小さな箱を手に取り、そうっと折り開く。中には緑色の翡翠の指輪が折り入れられていた。指にはめてみる。相変わらず少々小さいのが難だが直せない範囲では無い。昨日は水晶の首飾り、その前は鼈甲の腕輪である。どれも非常に貴重で高価な品々である。これだけは都であっても早々手には入らない。珊瑚は和紙を投げ捨て、指輪をはめ場を立ち去った。珊瑚が居なくなった事を確認し数人の下女が後を片づけ始めた。やる事が無い。珊瑚の容貌は太り、運動不足の為足は水ぶくれとなってきていた。 「珊瑚様、お父上様がお越しです」 「父が?何の用件で?」 下女の先導に従い、御簾のある部屋へと歩いて行く。例え受領である父であったとしても、この国で一番偉いのは都の覚えも目出度い珊瑚である。御簾も無しで会う事は無い。一礼して座に座る父、平和で栄養が良いため肥え太り目も下に垂れ悠然とした容貌をしている。どちらかと言うと都の人間と顔つきが似ていると言えるのかもしれない。珊瑚には五人の兄弟と四人の姉妹が居るが、どれも美形であり、縁談は引く手あまたであると言う。 「珊瑚、体調はどうだ。来月は産み月であるそうだから、産婆をこちらの館に常駐させるようにするが、どうするかね」 「そうして下さい。後何か用事はありますか」 「おいおい、親に対して急かさないでくれ。 |
| コ |
