

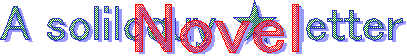
| 新しいカタチ 言い訳をするつもりは無いけれど諸事情あって、高級と言う名前の付いたセックスを伴う同伴倶楽部へと登録をした。面接をした人は私の顔と躰、そして”元ミス・日本”という私の肩書きを偉く気に入ってくれた様だ。 「合格です。明日から来て下さい」 ありふれた理由であるかもしれないが、半年勤務をすればアメリカ留学の費用を生活費から学費まで全て持つという条件は私にとってとにかく魅力的であったのだ。額は五千万を上限に全て倶楽部側が持ってくれるのだという。これだけあればアメリカの大学に入学して卒業するまで十分すぎる額であると言えるだろう。「新しい服でも買いなさい」と渡された封筒には後で開けてみると百万円入っていた。もう逃げられない。今まで勤めていた会社も辞め、完全に退路を断った。後はもう頑張るだけだ。 無論の事、私は処女では無い。十六の年以来五年間。片手の数程の男性と普通のセックスを経験して来ている。この数は多くもなく少なくもなくと言った数ではないだろうか。初めて派遣された先は、何と先輩と一緒であった。言われた通り指定の四星ホテルのペントハウスへと入り、シャワーを浴び下着だけになって主を待つ。先輩の下着は燃えるような赤に白いフランス製のレースが入ったゴージャスな物であった。私は日本製の白い下着。先輩はそれを咎める訳でなく、ベッドに横たわり、隣に一緒に寝るように促した。 「こういったプレイは始めて」 「はい・・・」 「いいのよ。緊張しなくて。あなたはここで横になっていれば大丈夫だから。後は任せなさい」 「分かりました。宜しくお願いします」 後で来たのだが、客は熟練者よりも、この仕事を始めたばかりと言うウブなタイプを好むのだという。しばらくしてお客が入ってきた。背後でシャワーを浴びる音が聞こえ、扉の閉まる音の次に、部屋へと入ってくるスリッパの足音が聞こえた。 「おや、今日はべっぴんさんだね」 見てびっくり。客は何と時の首相であった。あまりの驚きに声も出ないでそのまま横になっていると、首相はタオル地のガウンを脱ぎ、私を横に置いたままで先輩とセックスを始めた。首筋にキスをした後は下着をゆっくりと脱がし、胸を舐めるように愛撫する。高級な娼婦になればなるほど、客が娼婦の面倒を見る物だと言うが、その典型であった。感じてきた先輩が喘ぎ声を抑えようとしながら、体を左右によじる。胸から腰にかけての細いラインに手が伸び、一番大切な部分をなかなか触ろうとはしない。下半身の毛は綺麗に剃り上げられ、女性の目で見ても綺麗な形をしている。 正直に言うと隣で人がセックスをしている姿を見るのは初めてであった。Fカップの先輩の胸が左右に揺れ、あえぎ声が部屋中に木霊する。私の体温はそれに合わせて上がって行き、下半身は熱くなり、少しずつ濡れてきてしまった。 さぐるように、先輩と首相の下半身が重なり合う。先輩は完全に受けの態勢である。腰の動きも優しく、嫌らしさを感じない。最後は背後から激しく責められてフィニッシュである。首相は先輩がいったのを確認すると、優しくベッドへと横たえた。先輩の息は荒れたままである。首相はコンドームをおもむろに外し、新しい物と付け替えた。まさか? 「おまたせ、またせたね」 「え?」 「ほら、やっぱりこんなに濡れてる。我慢できなかったんだろう」 動揺する私を首相はそのまま抱き上げ、セックスを始めた。先輩の時とは違う、激しいセックスである。恥ずかしくて声を我慢している私を首相は容赦なく責め立てる。隣には同性の先輩が横になっているのに、である。 「ほら、いいんだよ声を出して。素直に感じてごらん」 「やめてください」 「体は正直だよ。ほらこんなに開いてしまっている」 責めは1時間以上にも渡った。私を完全にいかせ、征服した後首相は胸を揉んだまま正常居で貫き続けた。やっと解放されたのはホテルに入ってから三時間以上経ってからである。 「一人ではどうしても物足りなくてね、これで一ヶ月女無しで頑張れる」 首相はそう言ってスーツに着替え立ち去ってしまった。後ろ姿をベッドに倒れたまま見送る。はしたなくも感じてしまった私。それ以来私は普通のセックスでは満足出来ない体となってしまった。あの時感じた夢めくる感覚を味わいたくて、私は半年経った今もこの仕事を続けている。正直気持ちよくて、楽しい。そんな私悪い人間ですか? |
| コ |
