

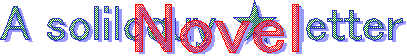
| アヒルの行列 1.出会い 「キミはどこの子だい?」 すっきりと晴れた。ある秋の日の出来事である。 自転車で遠出した先で、ふと見つけたペットショップの中、その黄色い物体は蠢いて居た。嘴は肌色で大きさは大人の拳ぐらい、鳴き声は「フィ・フィ」と甘く、優しい。羽はまだ成長しておらず形だけそこにあるだけであるが、目は黒く強い意志を秘めている。指で頭の後ろ辺りをこちょこちょと触ると気持ちよさそうにすり寄って来る。見たことが無い種類の雛であるが、これは何という種類なのだろうか。 亜美が檻の前に堂々と座り込んだのを見かねて、店主が駆け寄って来た。小さい店なので、レジの中から店の中が丸見えなのである。 「これはアヒルの雛です。大きくなれば羽は白くなり北京ダックのようになるはずです」 「そうなんですか、合鴨は飼って居るんですけど、普通のアヒルの子供を見るのは始めてでして。雛の色は黄色なのですね。まるで卵みたい! 」 「だったら飼ってみませんか? 既に一匹飼っているので有れば、飼いやすいと思いますけれど」 「既に二匹居るんだけど……」 頭の中に今財布の中に入っている金額を考えた。亜美の家では、兄弟が多い為か、小学校一年生の小遣いは月百円で、三年生は三百円と一律で決まっていた。今財布の中に二千円入っているから…… アヒルの値段は一匹千円。合鴨と同じ値段である。決して法外な値段では無い。しかし千円と言えば亜美の小遣いの三ヶ月分とちょっと。これを買ってしまうと暫く欲しい物は何も買えなくなる。 「まあいいや。後四ヶ月もすればお正月でお年玉が貰えるから。何とかなるでしょ。 ここで買わないと後々後悔する事になりそうな気もするし……私雌が欲しいんだけど分かります」 「それは分からないです。アヒルの雄雌は特に難しくて」 「ふーん」 鳥の雛はあっという間に成長する為、見つけた時が買い時なのである。一匹目の合鴨を飼い始めて既に三年。母ともそろそろ数を増やしたいね、という話をしていた矢先であった。現在亜美の家に居る二匹の合鴨は両方とも雌で、鶏と同じ様に毎日元気に卵を生んでいる。卵の大きさは鶏の卵の一番大きいエルエル・サイズと同じ位の大きさである。黄身は盛り上がり、箸でつまめる程新鮮な卵である。 「雄が当たるとね、ちとお母さんに怒られてしまうかもしれないから……良く選ばないと」 雄が要らない理由は勿論卵を生まない事と、雌よりも雄の方が荒いなど飼育して行く上で様々な理由があった。最初の雛選び、ここで失敗すると大変な事である。 「どの子が雌だろう。うーん」 結局亜美が選んだのは一番体格の良い雛であった。理由としては、今までの経験から考えてみると、体が小さな雛よりも、大きい雛の方が育てやすかった様な気がしたからである。考えてみれば、手乗りインコの雛よりも安いのだから、グラム単価で考えてみると、決して高い買い物では無い。 「ありがとうございました!」 紙製の箱に雛を入れて貰い店の外へと向かう。亜美にとってはペットの衝動買いというのは珍しい事では無い。亜美の家の庭には現在犬が三匹、アヒルが二匹、そして数限りない数のチャボ、烏骨鶏が生息していた。父の教育は至って簡単で、”自分の面倒を見きれない物を買うな”、である。自分で面倒さえ見れば、特に許可を取る必要は無い。全て自分で決めて、行動すれば良いのである。 しかし良く買うとは言っても、亜美の家族は絶対に屋台の鳥や動物は購入しない。 理由としては、買っても直ぐ死んでしまう事が多いし、成長した後も羽の色・形などが可愛くない事が多いからである。 亜美の家の近くで七月に”七夕祭り”と呼ばれる大型のお祭りがあるが、その際ウズラや鶏の雛が販売された翌朝は、ペットショップの前は雛が小山に置かれていることが多いのであると言う。お祭りで買ったのだが、飼いきれないと自宅に帰る前に気が付き、せめて良い飼い主に巡り会って欲しいと思い置いていく人が多い為らしいが、あまりの数にペットショップ側がお祭り開催委員に直談判を行い、七夕祭りでは数年間雛の販売が禁止されたのだと言う。人間の身勝手な欲望の為に消えていく命がいかに多いのだろうか。そして人はそれになかなか気が付かない。 ”育てる為に買う”。当たり前の事だが、そういった教育のせいか、鳥たちは家族それぞれの手によって、気がつくと増えていた、というのが本当の所であるのだが、普通の家ではそういった事は無いらしい。一般常識のハードルがちょっと違うのかもしれないが、そうした中で育った亜美にとっては、これが当たり前の事である。 「さて、独り立ち出来るまで頑張って育てないと!」 しかしながら、小さい雛の内は手間がかかる。亜美は家へと戻ると母に自慢げに雛の顔見せを行った後、早速綺麗な段ボールを用意して、百ワットの電球と綿、そして段ボールの中に入れるベッド用のティッシュの箱を入れた。母も新人の到着がとりあえず気になるのか、エプロン姿のまま、手を拭きながら亜美の側へとやって来た。 「ふーん。これがの子なの。可愛いじゃない」 「でしょ。思い切って買ってしまったんだ。お母さんには触らしてあげないよ」 「はいはい。自分で何とかする分には何も言いません。頑張りなさい」 母はさっさと立ち去って行ってしまった。準備万端整えると雛を段ボールの中へと移す。通常の状態であれば、母鳥が体温調整が余りまだ上手に出来ない雛を体の下に入れ、温めるのであろうが、母鳥が居ない場合、一番重宝するのはやっぱり百ワット電球である。迂闊に高価な電気マットなどを入れると水鳥であった場合、ビチャビチャにされてしまい、再生がきかなくなってしまう。裸の百ワット電球だけであれば、たとえ水をかけられても大丈夫であるし、たとえ破壊をされても腹は立たない。 「ほら、あったかいよー」 自然と電球の方に近づいて行く。寒くなれば電球に近寄れば良いし、熱くなれば離れれば良い。非常に合理的なのである。雛は亜美の手から離れ、「クークー」と声を立てて電球に近づき甘えていた。 「名前を決めないとね……あんたは黄色いからキミちゃんにしようか」 「フィー・フィーフィ」 一通り体が温まったのか、再び亜美の側へとすり寄ってきた。人の手にまとわりつき、体を寄せて甘える。自分の体が手にぴたっと吸い付くと、そのまま目を閉じて寝てしまった。やれやれ、二、三ヶ月で外に出て走り回れるようになるだろうけど……と亜美が寝たのを確認してから段ボールから手を抜くと、とたんにキミちゃんは目を覚ました。 「フィー・フィー・フィー」 どうも、抗議しているようである。「私も忙しいのよ!」と亜美はその場を立ち去ろうとすると更に声を張り上げ、段ボールの置かれた玄関中に響き渡るように騒ぎ続ける。寝付くまで側に居ろと???ここまで我が儘な雛は始めてである。 「うるさいわね。分かったわよ。寝付く迄よ! 」 手を入れたとたん、大人しくなり、すり寄って寝てしまう。手に触る産毛の感触は独特の物であり、下毛の無いその肌触りは強く力を入れれば壊れてしまいそうな程である。そんな事を三日も続けたであろうか、キミちゃんはようやく落ち着いて来たのか、一人で寝られるように成ってきた。「やっと蒲団で寝られる……」亜美は思いの外甘えん坊であったキミちゃんの動向に不安を覚えていた。こんなので大丈夫なのであろうか? 「次は小屋を作ってあげないとね」 2.先住民族・チャボ・キジ 犬小屋は普通に市販されているが、アヒル小屋となってくるとそうはいかない。以前家に出入りをしていた大工さんに頼んで木製の小屋を作って貰った事があったが、これは先住民族のチャボ達が使用している。 チャボがこの庭に住み着いたのは合鴨を飼う前、家に引っ越してきたばかりの事である。おばあちゃんの家にチャボが居たので、折角一戸建てに引っ越してきたのだから、砦も飼ってみてはどうか、と言われたのがキッカケである。一番初めにやってきたチャボのつがいは性格も良く、卵を良く産み、増えていった。チャボの群自体の性格は至って温厚であり、襲いかかってくる事は殆ど無い。頭も悪くは無く、庭に放していても夕方になると自然に自分の小屋へと帰っていくから手間がかからない。 手間がかかると言えば、やはりキジである。知り合いの猟師から貰い、母が飼育しているのだが、庭に離そう物なら、後も見ず逃げ回りまず小屋に戻ろうとはしない。恐らく見た目では一番綺麗なのであろうが、ペットとして飼うのには少々無理があった。 「キジが逃げて大変だったんですよー。本当にキジは懐きませんね」 「だったら、私が貰って育てましょうか?」 新聞配達のおじさんに亜美が愚痴っていると、とんでもない返事が返って来た。後日母に確認をし、引き取って可愛がって貰えるのなら構わないという旨を新聞配達のおじさんに伝えると、数日後段ボールを持ってキジを迎えに来た。 「こちらです。全部持っていきますか?」 「いただけるなら、全部」 キジの数は六匹であるのに、その段ボールの大きさは小さすぎるように感じた。しかしキジを扱うおじさんの手つきを見る内に、段ボールの大きさが小さい理由が分かった。おじさんは檻の中のキジを捕まえ、器用にその羽をくるっと円を描くように回した。するとあれ程じたばた暴れていたキジが大人しくなり、段ボールの中に収まるでは無いか。唖然とする亜美の前をおじさんは一礼してさっさと立ち去って行ってしまった。後日新聞配達のおじさんはこのキジを食べてしまった事を人づたいに聞くのだが、”可愛がる”と言っている以上、それ以上疑う余地は無い。 「あの人元々お肉屋さんなんですよ。ええ。食べたって言ってましたよ」 「え、本当に??? で、今あの人どこに居るんです?」 「そうだねえ、配達の仕事はとうに辞めたし、何をしているかは今となっては。じゃ、来月も宜しくお願い致します」 新しい新聞配達のおじさんから伝えられた衝撃の真実。実際キジは食べると非常に美味しく、好んで食べる人間も少なく無いらしい。父も韓国の斉州島でキジを撃ってきたという話をしていたから、実際に食べたこともあるのかもしれない。あまり知らない人にうっかり鳥をあげては成らない。亜美はこの一件以来、家族以外の人間に鳥を触らせる事を拒否するように成ってきていた。 「もう大人なんて信じられない!」 3.アヒル小屋 合鴨達は日中、庭で遊んでいる為、小屋の位置については特に日当たりが良い、と言うことは考慮しては居ない。とりあえずあれば良いという状態である。 現在合鴨達は亜美が作った下は土で、ベニヤ板を四方に囲んだ小屋と呼べない檻に住んでいた。上部は更に酷く、あり合わせの板を被せるだけである。 見た目は確かに悪いが無論良い所もある。下が土であり、簡単に移動が出来る為、下の土がフンで泥だらけになったら、すぐ別の場所に移動をすれば良いという点である。鳥を飼っていて一番辛いのはフンの掃除である。これがやらなくて良いので有れば、それにこした事は無い。お陰で騙し騙し三年使用しているが、やはりそろそろ新しい小屋を作ってあげなくてはならないだろう。 キミちゃんが大きくなる前に、木製では無くて、出来れば鉄骨の立派な小屋をつくってあげたい。材料を求めて庭の中をフラフラしていると、数年前から全く使われていない幼稚園用の対面式のブランコを見つけた。椅子の部分はプラスチック製なのでボロボロになってしまっているが、廻りの枠は丈夫な鉄製。これは良い材料を見つけた。 「椅子の部分を取り外して、廻りを網で囲ったらいけるかも!」 慌てて休日にホームセンターへ行き深緑色の鉄製の網を五メートル程とそれらを括る針金を買ってくる。小屋作成の予算は父が持ってくれた。とても亜美一人では払いきれない金額である。しかしやるのは亜美一人である。家に戻ってきた後はブランコの不必要な部品を思いっきり乱暴に取り外し、ブランコ全体を網で覆った。形が台形をしているので、網をペンチで面ごとに切り取ってから針金で巻き付ける。大事に成ってきた事を亜美の母は気がつき庭に出てきたが、特に止める訳でもなく、手伝う訳でも無く、隣で作成を見守っていた。 「鶏小屋作ってくれるのは助かるわ。キミちゃんの為にも。すぐに壊れないように丁寧に作ってね」 「大丈夫。見ていて」 小屋の完成までは一週間程かかった。完成した小屋は新品ではあるのだが、使用したブランコの鉄骨の部分、部分が既に茶色く錆びていたので、何だか完成した姿はみずぼらしい姿であった。 しかし機能面では前回の囲み式の小屋と違い、充実している。 正面入り口部分には細いタル木を使ってドアを作り、鍵も閉められる様にし、鳥たちが寝る部分には八百屋さんから貰ってきた木製の林檎の箱を置き、風が吹き込まないようにした。全面網にした場合、横風が吹いた場合、吹き抜けて可哀想なので、一面だけはプラスチックの薄い板を張り、風が完全に回り込まない工夫も施してある。これで雨の日も安心して小屋の中で過ごしている事が出来るはずである。 感無量。亜美が喜んで居る側で合鴨達が遊ぼう、遊ぼうとばかりに駆け寄ってきた。 「かもちゃん。チャーリー。やっと新しい小屋が出来たのよ!今日からここに住みなさい」 二匹とも毛色は全て茶色である。かもちゃんは一番の年輩者で、足が遅い。性格は至って温厚だが、他の鳥とは特に仲良くする様な事はしない。人間と遊ぶか一人で寝ているか、である。若いチャーリーは逆でチャボやワーレンなどと元気に餌を探しに行ったり、寝てみたりとかなり社交性が高い鳥である。 「キミちゃんもそろそろお外にデビューするから、その時はいじめちゃだめよ」 「ガーガー」と返事をしているようにも見受けられる。キミちゃんは「フィー・フィー・フィ」と鳴き、合鴨達は「ガーガーガー」と鳴く、この鳴き声の違いは品種による違いであるのだろうか??? 亜美は首を振って迫ってきたかもちゃんの背中を撫でながら、一人悩んでいた。 亜美が背中を優しく撫でると、背中の羽を平らにして、頭を低く下げる。ちょっとお尻の方を見ていると白い液体が出ていることに気がつく。この現象は決して人間に甘えているのでは無く、人間に”欲情”している現象であると言える。ひとしきり撫でるまでかもちゃんは人間を離してはくれない。本当は人間の世界では無く、同族の鳥の所に行き欲情行為をして欲しいと思うのだが、そうは上手くいかないらしい。とはいえチャボと合鴨が本当に結婚しても子供が孵るはずも無いのだが、 「はい、かもちゃんおしまいね。又遊ぼうね」 亜美は小屋の中に餌を入れ、合鴨を中に入れると扉の鍵を閉めた。あと一ヶ月もすればキミちゃんもこの輪の中に入っていくのであろうか、そんな事を考えると段々楽しい気分に成ってきた。日が暮れて庭に飛び散っていたチャボ達も小屋へと戻って行く。チャボの数が十匹を越えた時点で亜美は名前を覚えていないというよりも、付けないで居た。例え付けたとしても覚えられないのである。 チャボはたくさん居ても、この群の中には雄は一匹しか存在しない。その他は全て雌である。鳥は雌を取り合って本当に死ぬまで闘い続ける為、群の中に複数の雄を入れるのは通常危険なのである。又無論の事ながら血族婚も危険な事であり、孵す卵を生むチャボというのも決まっている。亜美の自宅で孵されたチャボは当然一匹しか居ない雄の子供であるから、その子供が孵す卵を生む事は出来ない。外から始めて雄と一緒にやってきた雌のチャボがそれに相当する。万が一でも混じってしまうと大変なので、油性のスプレーで羽に印を付け、その雌は管理するようにしていた。 小屋の中に通された一本の木にチャボが群がる。卵を孵している最中の雌達は木に登る事は無い。とはいえ冬場に卵を孵されると後で面倒を見る方は大変なので、現在は卵が孵らないようにゴルフボールを抱かせているのだが、卵を孵している最中は卵を生まないので、亜美的にはどうせ孵らないんだから、早々に諦めれば良いのに……と思っているのだが、チャボ達はそれを納得してくれない。 「はい。全員揃っているかな? もう閉めるからね」 明日又小屋が開けられることを知っているから、チャボ達は冷静である。亜美の家の庭に隣の家は存在しない。四方八方全て田圃である。迂闊に夜中に外に一匹で出ていくとイタチや蛇などに食べられてしまう危険性があるのである。 「やれやれ、さー今日の夕食は何かな???」 4.凶暴なアヒル 「亜美お久しぶり!」 季節は寒い冬を通り抜け、夏を迎えた。 亜美の友人の由香が遊びに来たのである。玄関まで迎えに行った亜美は即由香の背中に隠れていた。何やら慌てている風情である。 「どうしたの?何?何??」 「危険なのよ。早く逃げて!」 「逃げるって、何から??」 キミちゃんから、と言う前に由香はキミちゃんに襲われ、足をしこたま噛まれていた。ペンチで肉を掴んで引っ張ると言ったら分かりやすいが、白い由香の足に青い痣が浮かび、キミちゃんは更なる攻撃をしかけようと突進してきた。唯一の武器である頭を下に下げ、白い爆弾と化したキミちゃんが容赦なく人間を追いかける。 「きゃあ!」 危機をようやく察した由香は玄関に向かって走り出した。家の中に入り噛まれた部分をさする。「いやーお陰で無事だった」と知らぬ振りをする亜美に由香は力強く責め寄った。 「あれは一体何?前はあんなに乱暴じゃなかったと思うけど、キミちゃんどうかしたの?」 「どうも繁殖期に入ったらしいんだ。私はともかく外部から人間が庭に入ってくると凶暴になってしまって、そんな時はちゃんと逃げないとうっかり私も襲われてしまう」 「で、私の後ろに隠れたと」 「標的を間違えない為にね」 酷い飼い主も居た物だ、と階段を登り、亜美の部屋へと入る。二階のベランダからは合鴨のチャーリーを引き連れて悠々と庭を歩き回るキミちゃんの姿があった。黄色い毛はとうの昔に抜け落ち、今は白い丈夫な羽に覆われている。 「湿布貼って置いた方がいいと思う。分かっていると思うけど、帰りは走って出た方が」 「言われなくてもそうするわよ!」 「キミちゃん足は遅いから。そして首捕まれると何も出来ないから、慌てさえしなければ特にトラブルは起こらないんだけどね。弟なんてキミちゃんに襲われて、泣きながら庭から帰ってきたから」 「アヒルに庭を占拠されて、悔しくないの」 「いいのよ。アヒルは番犬にも成るんだから」 実際、国によっては、アヒルは食用としてではなく、番犬としても使われている。攻撃能力は犬に比べ皆無に等しいが、泣き叫び、主人に知らせると行った意味合いでは犬よりも遙かに優れた能力を持っている。 「雌だけの時はこういった習性は無かったのだけど、雄が入ったとたん急にテリトリー意識とかが生まれたみたいで、困ってはいるんだけど、家族だけの時は襲われる事は無いから大丈夫よ」 「え、でもキミちゃんて、雌じゃなくて雄だったの?」 「そう。ついに見てしまったのよ」 外見上水鳥は性別が分からない。亜美が見てしまったのはキミちゃんがチャーリーの上に乗り、お尻の穴から生殖器を付きだしている姿である。あんな所に隠してあったんだ……大事な物だからね……と納得するよりも、自分が雛選びに失敗した事にようやく気が付いたのである。 「今回は失敗してしまったのよ。いやー見た目分からないから」 「じゃ、これからもどんどん増えるって事?」 「そうはいかないと思う。どちらかと言うと合鴨って卵孵すの下手な種類だから、人間がちょっと邪魔しただけで諦めちゃうのよ」 「でも、一度は孵してみるつもりなんでしょ」 「一匹、二匹位はするかもしれない。そのぐらい増えたからって大した事は起こらないし」 「更に凶暴なアヒルが増えると」 「ま、それもまた人生! と」 又合鴨などの種類は第一種雑種、つまり合鴨とアヒルとのアイノコは産まれても、第二次雑種、つまり合鴨とアヒルのハーフにアヒルが懸かるような状態になっても、遺伝子学上、雛は産まれないと言われている。現在人の手が水鳥の住環境を犯し、水鳥の種類間の縄張りが混乱してしまい、第一次雑種の鳥が増えてきているのだと言う。傍目には水鳥の数が増えているようにも思われるのだが、実際には第一次雑種の鳥は生を次の世代に伝えることは出来ない。自然とその種類の水鳥は滅びの道を辿ることになるのである。珍しい鳥が水辺に居るのを頻繁に見かけるようになったのなら、そういった意味合いも含めて、注意して観察し、必要であれば早めに保護の手を差し延べる事も必要であるのかもしれない。 5.アヒルの雛誕生! キミちゃんとチャーリーのカップリングは成功し、亜美はその卵二つをチャボの小屋へと入れた。チャボの卵は合鴨の卵の半分程の大きさであるが、今までの経験から考えると、これで無事卵は孵るはずである。チャボは卵孵しの名人であるから。 「君たちが失敗したら、足温器で孵すから、ま、気負わないで頑張ってくれたまえ!」 初代のチャボ一家は孵卵機では無く、亜美が昔使っていた足温器で卵を孵したのである。一日に何度も展覧し、水分を与え、数十日。これまた結構上手に卵が孵る。無論これは人間の手間がかかるので、最終手段となるのであるが、 結果は大成功。生まれてきた雛は二匹、一匹は黒の背中に黄色い産毛を持った雛と、もう一匹は母親のチャーリー同様全身茶色の雛である。孵った後は人間の手に引き取り、外を一人で歩き回れるようになるまで家の中で育てる。一匹だけで育てたキミちゃんの時と違い、仲間が一人居る場合は、思いの外甘えて来ず、二匹で百ワット電球の下で抱き合って寝る姿がよく見受けられた。懐かないと言うのでは無いが、キミちゃんの時のようにベタベタといった幼児期では無かった。 「これでキミちゃんもお父さんになったんだから、少しは大人しくなるでしょう!」 そんな事はあり得なかった。外に出かけるようになった二匹の雛、黒い毛に白い腹色のアヒルはクロちゃん。全身茶色のアヒルはシマちゃんと名付けられた。キミちゃんとチャーリーに合流すると、何の違和感もなく一つの群としてまとまり、行動を始めた。群も四匹ともなると立派な物である。広い庭を駆け回り、餌を探す。亜美の母はうっかり庭に種を蒔けないようになってしまった。蒔いた次の日には必ずこのアヒルぐれん隊が蒔いた場所を襲い、穴だらけにしてしまうからである。アヒルの嘴は大きく乱雑だ。チャボの様にこっそり隠れて食べると行った事はしない。 「この庭って何坪ぐらいあるの?」 「三百坪ぐらいかな、殆ど動物の王国です」 キミちゃん達が居ないことを確認して、由香が遊びに来た。大分要領が分かってきた様である。 「怖くない?こんな庭で」 「別に。暇しないから楽しいし、まず知らない人とか泥棒が入らないのが助かるし。近所の人はまず側に寄らないからね」 「怪しい家だからね」 「ほっといて! 」 二階から庭を眺めると、アヒルの群とは離れて一人寝そべるかもちゃんの姿があった。キミちゃんは最古参のかもちゃんが大嫌いなのである。理由は全く分からないが、人間に懐くかもちゃんがただ単に気に入らなかったのかもしれない。餌場にかもちゃんが現れようものなら、全力で噛み付き、側に寄せ付けようとはしない。 「キミちゃん!かもちゃん苛めちゃ駄目って教えてあるでしょう!」 アヒルは犬と違い、人間の言った事を学習する事は出来ない。 かもちゃんの身の安全の為、餌場は別に移され、遊ぶ時間帯も分けられるように成ってきた。かもちゃんも既に五歳。老年である。羽は目に見えてパサパサし、目の色は次第に濁ってきていた。 「クロちゃんが雄で、シマちゃんが雌だと言うことは分かったんだけど、もう一つ分かった事があるんだ」 「何が?」 「鳴き声よ。かもちゃんとチャーリは「ガーガー」と鳴き、キミちゃんとクロちゃんは「フィー・フィー」と鳴くのよ。どうも鳴き声で雄雌が判別できるみたいなのね」 「それは知らなかった。でもアヒルって雄同士で仲良く出来るんだね」 「品種的にかなり家畜化が進んでいるからかもしれない。仲良くやってるよ」 元々アヒルは川や湖など、水辺に住む生き物。人の住む土ばかりの土地に住む生き物では無い。生まれて一年も経たず、キミちゃんは普段は目に見えない部分が奇形化し、真っ直ぐに走れない体へと変貌を遂げて行った。足の裏の部分が丸く腫れ、ボールの様に成ってきてしまったのである。 「キミちゃんどうしたの!一体何が起こったの!」 病院へと連れていったが、原因は巨大化した為足がその体重を支えきれなくなったからだと判明した。近年アヒルを巨大化させてしまい、足が奇形化する病気が蔓延しているのだと言う。近所の神社にキミちゃんと同じアヒルが居たことに気が付き、足下を見ると同じように腫れている。現代病がついにアヒルの世界にもやって来たのである。 「キミちゃん!」 もう直らない。でもキミちゃんはそんな体でも庭を歩き回る事を止めなかった。そして苛められていたかもちゃんもそんなキミちゃんを苛めたり、追い回したりと言った事はしなくなった。庭に平和が訪れた。亜美はもうアヒルの数をこれ以上増やすつもりは無かった。後は最後まで面倒を見た後はそれを最後にしよう。そんな亜美の目の前に三つの卵が持ち込まれたのである。 6.懐かない野生の鳥・カルガモ 「これ、何ですか? 」 「カルガモの卵らしいんだ。田圃で拾ったんだが、振ってみたらもう固くなっているみたいで、このまま捨てるのも何だし孵して貰えないか?」 「孵すんですか? 」 「出来ないかい? 」 「出来ますよ。そういった事があったら家に任せて下さい。でも孵した後はどうするんですか? 」 「こちらで面倒を見て貰うか、無理だったら外に離してやってくれ」 卵の大きさは合鴨の卵よりもずっと小さい。丁度チャボの繁殖期とずれていた為、足温器で卵を孵す。既にかなり温められていたらしい、卵は十日程で雛になった。クロと黄色のシマシマの文様。確かにこれはテレビで見たカルガモである。 テレビなどでは平和のシンボルとして扱われているが、田圃をやる人間にとってカルガモは田圃を荒らす害鳥である。近年は合鴨農法と言い、無農薬農法の一つとしてもてはやされるように成ってきているが、それらの作業をカルガモが行うことは不可能なのである。まず大きな違いは合鴨と違いカルガモは飛んで逃げる事が出来るという点である。餌が無いから害虫を食べて頑張ろうなどとは絶対に思わない。さっさと飛び去って美味しい魚や作物などを容赦なく食い荒らすからである。 「アヒルや合鴨とどこが違うんだろう。カルガモは」 まず、性格は全く違った。人間には雛の内から全く懐くことは無かった。外に出しても結果は同じ。餌を食べる時さえも人間に対して警戒を行い、ストレスが溜まっているせいか、羽は常に汚れ放題であり、自分で整えようともしない。臭いまま、汚いままである。 これは飼えない。外に放すべきだ。亜美は羽が成長したのを見計らって外へと離した。本能に植え付けられた行動は恐ろしい。あっという間に庭の外に飛び立ち、見えなくなっていってしまった。残されたのはフンだらけの仮住まいだけである。 「もう金輪際カルガモは飼わないから!薄情者!!」 しかしカルガモ達は亜美を嫌いではあったが、疎んじてはいなかったらしい。一年後、カルガモ達は亜美の家の側の田圃へと帰ってきて、夜などはアヒルの餌を狙っている事が判明した。朝うっかり早く起きると大きく成長したカルガモと出会う事がある。遠くを見つめる黒い目に、綺麗に整えられた上羽。野生に戻った後も覚えていてくれる事に、亜美は感動を覚えていた。 「鳥はやっぱり難しいね」 その年の発情期が終わった後、カルガモ達は自分たちで雛を孵したらしい。余り飛び回らなく成ってきたかな、と思ったある日、亜美の家の玄関にカルガモの雛が座っていた。 「ガーガーガー」 どうやら迷子になった、と言う風情なのである。捕まえて家の中に入れると大人しくしている。まるで親鳥に「万が一困った時はこの家を尋ねなさい」と言われてきた様である。飛び立てるまでに成長すると、相変わらず薄情に飛び立っていくカルガモ。しかし、これはこれで良いサイクルなのかもしれない。 「……。又来年迷子にならないでよ!」 7.歌の上手な鳥・インコ 亜美が庭の外でアヒルの増殖に明け暮れている頃、亜美の妹清花は家の中で黙々とインコを育て喜んでいた。亜美も一度友達に成鳥のインコを貰い育てたことがあるのだが、小屋から小屋へ移す際、指をしこたま噛まれてしまい、それ以上繁殖させたりと言うことはしないでいた。アヒルの押さえ込んで引っ張るタイプの噛みつきではなく、噛んでえぐると言ったタイプの歯痕は暫く直らない。しかし清花に言わせると噛まれるような事をする人間がいけないのだと言う。 「亜美ちゃんは優しくないから、インコが怒ったんだよ」 「ちょっと、それは言い過ぎじゃないの?」 清花が飼っているインコは現在二匹、一匹は小学校一年生の時教室で飼っていた物を、一番可愛がっていたから、と貰った物である。二匹目は貰ったインコが雌であった為、カップリングさせようと雛の状態で買ってきた物だが、成長して一緒の小屋に入れると、何と古参の雌が雄を喰い殺そうとしたのである。慌てて引き離したものの、雄は頭の毛が殆ど抜けてしまい、半死状態。以後も何とか繁殖させようと挑戦したのだが、半死状態を繰り返すばかりで、先へと進まない。かくして小屋は二つ、鳥は二匹という不経済な状態がずっと続いていた。 朝一番に庭の風当たりの良いところに駕籠を出し、夕方には部屋へと戻し小屋に光りが入らないように布をかける。体力が小さく体が弱い為、体内時計管理は飼い主がしっかりしてあげなければならない。清花は自分の部屋の掃除は殆どしなくても、インコの小屋の掃除だけはマメに行っていた。本当にインコが大好きなのである。 「アヒルなんて好きな亜美ちゃんの気持が分からないわね」 「インコなんてつまらないわよ!」 インコは飼い主以外には全く懐かない。亜美は極力清花の部屋へは近づかないようにしていた。うっかりインコを放している時に部屋に近づくと、インコに襲われるからである。「やめてよ」とうっかりインコに暴力を加えよう物なら、もっと凄い腕力で清花に殴られる。耳を多少カリカリ噛まれても、セーターに穴をあけられてもとりあえず静止状態で大人しくしていなければならないのである。 「清花。お願い早くインコ取って!」 「うるさいわね。ほらチビちゃんおいで!」 清花の声に従ってインコは定位置に飛び立って行く。アヒルには全く躾が入らないが、インコにはかなり躾が入るようである。成長しても人間に甘えるし、第一に言葉を話せるのが驚きである。 「インコって話せるの?オウムが話せるのは知っているけど」 「話せるわよ。歌も上手だし」 「チビチビチビ」と自分の名前を連呼したり、「オハヨウゴザイマ」「サヨウナラ」「ソレハイヤーダナ」とかなりの芸達者。もう少し語彙が増えればテレビに出る事さえも夢では無い。しかしいじめられてばかりの雄は全く話さない。毎日寂しそうな目をして、小屋に止まっているばかりである。 「こっちの子って何か芸するの?」 「ナナはしない。でもねこの子は脱走しないのよ。ずーっと側にいるの」 先日外の空気を吸わせようと、外の庭にインコの小屋を置いていた時の事である。うっかりインコの小屋の扉を開けたまま家に戻ってしまったのだが、ナナは小屋の上にずっと座っていて、逃げるような事はしなかったのだと言う。一般的にインコは脱走の一回目のチャンスには逃げないが、二回目はさっさと逃げていく生き物だと言われるが、ナナはうっかり飼い主の意図に従い、「やれやれ、又あいているよ」とばかりに小屋の上に停まって待っているのだという。 「羽切っているから飛べないんじゃないの?」 「切ってない。だから飛べるはずだよ」 手乗りのインコは脱走を根本から禁止する為に、飛ぶための羽の一部を切ってしまう事がある。無論飼い主の好みとなる部分なのだが、切らなかったが為にインコが逃げ出し、野良となり、繁殖しニュースとなる事が多々ある。インコは元々熱帯に住む鳥である。地球全体の温暖化が進んでいる今、インコは日本の冬でも元気に越して行くのである。 「逃げないのは良いことだけどね、それだけか芸は」 「アヒルはもっと何も出来ないでしょ。比べないでよね」 「あの鳥達は家を守っているのよ。守って貰ってばかり居るインコと一緒にしないで」 同じ血の流れる姉妹とは言え、好みは全く違うのである。 8.卵の美味しい烏骨鶏 そんな亜美と清花の母はこれまた別の生き物を飼っている。烏骨鶏である。元々はペットショップで一匹五千円で購入したのだが、これが現在チャボの数を超える程にまで繁殖している。アヒルの卵は大味で美味しくない、やっぱり今の時代は烏骨鶏の卵が一番よ! と言うのだが、食べてみればその違いが良く分かる。美味しい。 「で、こんなに鳥を増やしてどうするの?」 「どうするのって、卵を取るのよ」 亜美と清花の母である。趣味の幅はお金がある分計り知れない。増やし方も大雑把である。まず有精卵である卵を、チャボを使って孵し、ある程度成鳥させる。烏骨鶏の毛色には黒と白があるが、それら毛の色は雄雌とは関係がない。雄雌が分かってきた時点で雄は卵を生まない為、欲しい人にあげてしまうのである。あげられた鳥は……例外なくそのまま首を捻られ食べられてしまう。プロは雛の雌雄判断が、まだ雛の時点で分かるそうだが、そうした場合は分かった時点で首を捻られ、食べられてしまう事になる。無惨な増殖方法である。 「とは言ったって、雄を残して置いたら殺し合うのはあんたも良く知っているでしょう」 「でもさ、もう増やすのやめてよね、可哀想だよ」 「可哀想って、これが今の時代の摂理なのよ」 何気なく食べるスーパーの卵の裏には、生後まもなく殺された雄の雛が隠れている。目の前でそれを現実として見ると強烈な刺激があった。運の良い鳥は小学校に貰われていったり、近所の家に貰われていったりとして行ったが、その数もたかが知れている。繁殖の効率を考えると、やはりこうした方法が有効で有ることは間違い無いのである。 亜美の家に多数居る鳥の中で、一番外部の人間に人気がある物はというと、やはり母の烏骨鶏である。雛で無くてもいいから、卵だけでも分けて貰えないかという話は折々に言われる。自宅の鳥に抱かせて孵すから、と言うのである。母は殆どの場合そうした申し出は断ってしまう。無論それは卵が貴重であるからである。人にあげる位であれば子供達に食べさせる。それは当たり前と言えば当たり前の事であった。鶏がほぼ毎日卵を生むのに対し、烏骨鶏は二日に一度程度、鶏の半分ほどの卵しか生まない。しかし味は格別。スーパーなどでは一ケ五百円程で販売されているが、その価値を考えると高すぎる値段では無いのである。 「お母さんは趣味でやってるんだから、あんたたちにとやかく言われる事は無いわよ。最近近所の人に卵を分けて上げたら、それは喜ばれたわよー」 「何個あげたの?」 「四個よ。勿体なかったかしら」 小さな卵四ヶで一体何が出来るのだろうか……しかし亜美のお弁当箱の中に入った烏骨鶏の卵焼きの味はやはり格別であるので、それ以上嫌味を言う気にはならなかった。 「アヒルの雄同士は喧嘩しないのね。 毎日庭を見ても、仲良くやってる」 「そう。うちは仲いいよー。烏骨鶏とは大違い」 鳥による性格の違い、それは人間の性格と同じように違うのである。 9.現れた敵 四方は田圃に囲まれた庭に鳥がとにかく鳥がウジャウジャいるのである。それを狙う者が現れるのは致し方の無い事であったのかもしれない。 一番初めの被害者は、うっかりもののチャボの雛であった。ようやく庭で走り回れる程度にまで成長したチャボは嬉しそうに駆け回るだけでなく、うっかり庭の柵の外に飛び出してしまったのである。柵と柵の間は十センチメートル。チャボの雛にとっては、柵は柵としての用を為していなかった。 「帰って来なさい!」 慌てて亜美と母が外に駆けだし、稲の植わった田圃の中に分け入る。水が入っているからぬかるんで雛の所まで足が届かない。ピヨピヨと鳴いているので大体の場所は分かるのだが、あざ笑うように逃げ回り、掴まらない。紐を付けて母鳥を連れてきてしばらく放置してみるが、側には寄ってくるものの、人間が近づくとあっという間に逃げていってしまう。田圃は楽しい遊び場だと勘違いしているのである。夜になると恐ろしい動物が現れるというのに…… 「知らないよ。あんた夜になって食べられちゃっても!」 夕方になって捜索は打ち切られた。母鳥はそのまま置いておくと危険なので、家の中に連れていく。長い夏の夜の日が暮れた。雛はまだピヨピヨと鳴いている。今日は田圃の畦で夜を明かすのだろうか。 ちょうど亜美が寝る前に牛乳を飲みに台所に来た時の事である。外で雛の「ギャー」と泣き叫ぶ声が聞こえ、何か引きちぎるような声も続けて聞こえて来た。「やられたか!」と慌ててサンダルを履き縁側から外へ駆け出すが、もう庭の外は静寂に包まれている。翌朝、起きて直ぐ亜美は現場へと向かった。散らかった鳥の羽に無数に落ちる血の痕、群を離れた鳥がどのような運命を辿るのか、それは自然界でもふと一歩離れた田圃においても変わらない様である。 「だから帰って来なさいと言ったのに……イタチめ!」 亜美は犯人を見たわけでは無い、しかし近所に生息している生物でその様な乱逆な事をするのはイタチしか考えられなかった。田圃や用水路の脇に巣を作り、鳥を荒らす生き物。そして今回の事件でイタチは味をしめたらしかった。鳥は美味しい。もう少し食べてしまおうか……翌日の夜から、小屋の隙間に入り込み、小さい雛から一匹づつ食べては逃げると言うことを繰り返し始めたのである。 「またやられた!今度は烏骨鶏が!」 羽と鶏冠と血の塊が庭に飛び散っている。慌てて烏骨鶏の小屋を確認し、入り込めないように補修する。今回やられたのは成鳥である。他の鳥も怯えてしまい、昼間もあまり庭を駆け回らないようになってきていた。小屋の入り口にイタチの嫌がる光り音の鳴る物を吊し、夜時間があれば、何度も小屋を巡回する。亜美のこうした努力が実ったのか、イタチの暴挙は収束に向かいつつあった。昨日は全員無事、今日は……と向かったアヒル小屋で事件は起こっていた。今までアヒルはイタチの被害にあった事は無い。大体個体の大きさがイタチの二倍ほどある為標的には向かなかった、というのが理由として考えられるが、だからといっては何だが、亜美のマークも甘かった。小屋の補修は簡単にしただけで、特に注意はしないでいたのである。 「チャーリー!」 アヒル小屋の中には長い首から血を流し、倒れている合鴨、チャーリーの姿があった。旦那であるキミちゃんも大分慌てているが、側に寄るわけにもいかず困っているらしかった。チャーリーを抱き上げようとすると、キミちゃんが邪魔して上手くいかない。本人は自分の奥さんを守っているつもりらしい。 「キミちゃん。チャーリーは私に任せなさい。何とかしてみせるから!」 抱き上げてみるとしっかりとした息があった。傷を受けた首の部分に赤チンを塗り包帯を巻く。傷も牙が一本深く入っただけで、そう大きくは無い。どうやらイタチはアヒル小屋に入り込み、首を引っ張って逃げ出そうとしたのだが、チャーリーの体が大きすぎてつまり、その穴から逃げ出す事が出来ず、結局は諦めた様であった。 数日家の中で養生するだけで、チャーリーの容態はすっかり良くなった。アヒル小屋の補修を徹底的に行ったのは言うまでも無いが、もう二度とイタチが鳥を襲えないよう、亜美は夜の間犬を庭に放すことにした。夜来客が来たとき大変な事が起こる可能性もあるが、こうなってくると鳥たちの命を守る為、格好いいことばかり言っていられない。 「夏が終われば、秋になって稲が刈り取られればイタチも襲ってこなくなるから」 やはり田圃の中、身を隠す場所が無くなると、やって来にくくなるらしい。 かくしてイタチの季節は終わり、次の敵が現れた。 10.空からの敵 稲が綺麗に刈り取られ、稲穂が綺麗に整えられ出荷されている。 秋は実りの季節であると共に、繁殖の季節である。アヒル小屋の増員は無いが、相変わらず烏骨鶏の数は増えている。そんな中、亜美の家をぐるぐると巡回する鳥の一群があった。黒く大きく羽を広げた鳥、望遠鏡で覗いてみると、嘴が鋭くとがっているのが良く見える。かなりの上空からぐるぐる庭を廻り、確かに何かを狙っている。 「お母さん!何か変な鳥が空に居るんだけど!見て!」 「え?」 母が慌てて庭先に飛び出してきた。そして上空を見るなり、亜美に庭に出ている鳥を全てしまうように指示した。昼間は出ていて良いと決まっているので、鳥たちはそう簡単に納得して小屋へは戻ってくれない。普段あげない上等な餌を使ったり、無理やり走り込んで捕まえたりと試行錯誤の末、鳥を全て小屋の中へとしまう。全てが終わった後で亜美は母に尋ねた。 「あれは一体何?」 「トンビよ。小さな動物とか小さな鳥なんて、空から一発で捕まえられて食べられてしまうから!」 「あれがトンビって言うの? 始めて見た!」 庭に鳥が居なくなったのを確認すると、トンビ達は立ち去って行ってしまった。明らかに亜美の家の鳥たちを狙っていた様である。 「亜美、これからは外に鳥を出すときは見張っていないとだめよ。取られてしまってからではもう遅いのだから」 「そんな事言ったって、一日中外に出ているのなんて不可能よ!」 しかし以外にもトンビは一度も襲っては来なかった。 何度か上空を飛び回るものの、最終的に庭に降りて鳥を連れ去るようなことは無かったのである。根性無しであったのか、まめに人間が見張っていたのが良かったのかは不明だが…… 11.最後の敵 季節は危機感を煽りながら冬を迎えた。雨が降ろうと雪が降ろうと鳥たちは外の庭で暮らしていた。亜美はと言えば相変わらずノンビリと小学四年生の生活を楽しんでいた。亜美の家の側には公園も何も無いけれど、家に戻れば家族が居て、鳥達が居た。家へと向かう舗装されていない土の道を一人で歩くのもすっかり慣れた。ふと見ると赤いジャンバーを着た、見慣れないおじさんが前を歩いている。誰だろう?そんな事を考えながら家の玄関の方へと歩いて行き、門を開けた。すると後ろを走っていたおじさんが突然亜美に襲いかかってきたでは無いか。驚いて亜美は門に手をかけたまま倒れてしまった。声が出ない。助けを呼ぼうにも声が……おじさんの手は亜美の下半身へと廻ってきた。体が動かないどうしたら……声にならない声が頭の中を木霊する。 「た・す・け・て・」 背後から亜美は気配を感じた。亜美と門の隙間を一気に駆け抜け、低い姿勢からおじさんに飛びかかる白い物体。それはまさしく亜美の一番弟子、キミちゃんであった。 「キミちゃん!」 呪縛が解けた。声が出るようになったのである。キミちゃんと共にチャーリーとクロちゃんもおじさんへと飛びかかって行った。慌てておじさんは鳥たちを振り払い、逃げ出して行った。後を追いかけなくては……とも思ったが、足がすくんで前へと動かなかった。何があったんだろう、きみちゃんはおじさんを追いかける訳でもなく、亜美の足下へと戻ってきた。 「ありがとう。まさかキミちゃんが私を守ってくれるなんて思わなかった」 心配そうな顔で、首を少し横に向けながら亜美を見つめている。亜美は一瞬、時間が戻り雛の状態のキミちゃんに出会ったような気がした。亜美が無事なのを確認すると、キミちゃんは何も無かったかのように、他の鳥たちを引き連れ、庭へと戻って行ってしまった。慌てて亜美も立ち上がり、家へと入り母に事情を伝えたのだが、痴漢の犯人が捕まる事は無かった。どうやら亜美が見た人物は痴漢の常習犯であるらしく、被害者は亜美の他数人上がっているようであった。 「軽自動車で見知らぬ土地へ来て、痴漢をして帰っていくという犯罪が最近増えて居るのですよ。お気をつけて」 夜中にやって来た警官はそう言って立ち去って行ってしまった。その日から数週間、亜美は母に小学校へと迎えに来て貰い帰宅するようにした。家へ戻れば鳥や犬たちが守ってくれるが、その合間はどうする事も出来ない。恥ずかしく母の手を軽く握りながら、何を話す訳では無く川沿いの遊歩道を歩く。すると次第に飼っている鳥たちの話しになっていった。 「キミちゃん達を大切にしてあげなきゃね。亜美を守ってくれたんだから」 「うん。いつまでも」 いつまでも、いつまでも、流れゆく川のようにこれからも、亜美とアヒル達の生活は今もまた続いて行くようです。 |
| コ |
