

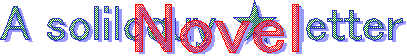
| 毒殺師 雨が降る。 長崎の雨は風流だな、と京育ちの朱がねは常々思っていた。 盆地である京都で雨が降るとどうしても湿気が籠もり、衣服が肌に張り付くようになってしまう。しかし長崎の日本らしからぬ温かい気候の中では、上がった気温を冷たい雨が下げ、非常に心地よく感じる事が多い。 朱がねの基本的な考え方としては、とにかく雨の日は外に出るべきでは無いと思っている。わざわざ何故雨の日に苦労をして衣服を濡らして歩かなくてはならないのだろうか、こんな日はのんびり家で書を読んで過ごすに限る。 「先生はどうせ、今日の医院はお休みでしょ」 どうせが余分。通いの書生が分かっていても必ず嫌味のように家へと確認にやって来る。 秋雨の季節は特に休みが多くなる。一応確認の意味で片手を背後に振る。特にあくせく働く理由も無い。と思っていた矢先、家の中に息を切らした二人連れが突如として風通しが良いようにと開けておいた玄関口に入って来た。 「ん?」 濡れずみの体の滴を払い、傘を折り畳む。走って来たと言うことは病人ではあるまいが……朱がねは重い腰を上げ、玄関の元にのたのた本当に厭そうに歩いて行った。元より玄関の鍵を閉めていなかった朱がねが悪いのであるが、家の中に人が突然走り込んで来るという事は例え病院内であったとしても、決して気分の良い事では無い。 「何か用事かい。今日は医院はお休みだ。明日晴れたら来てくれ」 「先生。先生ですかい」 訛が少し残っている。連れの子供はまだ未成年である。見た感じは一六、一七であろうか。髪には月代すらまだ剃ってはいない。表情は幼いが眼孔はしっかりとしていて姿勢も良い。指の爪は必要以上に綺麗に切りそろえられ、何やら端の方は白く汚れていた。服の仕立ても決して悪くは無い。これは決して単純作業に従事している使用人とは明らかに違う風情を醸し出していた。 「お願いがありまして、遠方はるばる江戸から参りました。どうか私のお願いを聞いて下さい!」 「お願い?明日にしてくれ、俺は忙しい」 「先生!お願い致します」 わずらわしい事は大嫌いだ、と手を振り払うふりをした所、女は慌てて懐から何重にも紙を巻き付けた封書を取り出し、朱がねの前に差し出した。表書きには”弟へ”と書かれている。朱がねの兄弟は姉が二人居るのみである。内一人上の姉は字が書けないから、書いた人間は自然に誰か知れてくる。 「先生のお姉さんから預かってきました。どうか私の話を聞いて下さい!」 誰にも世の中で一人や二人頭が上がらない人間が居る。京に住むこの下の姉は朱がねにとって一番近い肉親であり、恩人であり、誰よりも尊敬する人物であった。 家計を支える為、下の姉、舞は十二の年に京都の茶屋へと年季奉公に出、縁あって舞妓となった。年季奉公が終わった今となっても、すっかり京の空気が気に入ったのか、田舎には戻らず京で衿変えをし、芸妓として働いている。実は朱がねの寺子屋、私塾への学費、そして長崎の医院開業資金までも下の姉舞が出資しているのである。 舞は朱がねの事を「手間と金ばかりかかるぐうたら男」と称する。実際その通りなので朱がねは舞に全く頭が上がら無い。とにかく、その姉からの紹介状であれば、どんな理由であっても読まない訳にはいかない。 「とりあえず、あがってくんな。向かいのおばちゃんにお茶入れて貰うから」 「ありがとうございます」 女は頭を下げ、子供にも頭を下げるように軽く促した。 「昨日はどこへ泊まったんだい」 「場所が分からなかったので、二日前からここから近い旅籠に宿を取っています」 何度見ても微妙に違和感がある。どうみても親子では無い。 子供は仕方なさそうに、ぎこちなくも頭を下げ、二人は雨に濡れた草履を脱いで座敷に上がって来た。それを確認してから、朱がねは入れ替わり玄関へと向かった。ぽたっ。ぽたっと木の廊下に二人の足跡が付く。 だから雨の日は出かけない方が良いのに……土間にて二人の後ろ姿を見送り、向かいのおばちゃんにお茶を頼む。一人暮らしとはいえ回りの人間が何やかんやと面倒を見てくれる為、さしたる苦労は少ない。代わりに風邪を引いたとき、火傷をした時には無料で薬を処方するだけである。 相互扶助でありながら余計な詮索はあまりしない。人間関係を長い間続けるにはこうした関係が一番である。 「おばちゃん、茶頼めないか」 「あいよー。すぐ持ってくよ!先生」 茶碗などの茶器は朱がねの家にあるから、持ってくる物は熱い湯と茶葉の入った急須のみである。手際よくさささっと中に家に入り、急須にお湯を入れ、会釈をして立ち去って行く。ありがたい。晴れたら散歩がてら茶菓子でも買いに行ってお礼に差し入れするようにしよう。 「で、この雨の中何の用件だい」 両手にてうやうやしく差し出された紹介状を受け取る。風流な平仮名で墨の色濃く書かれた手紙。確かにこの筆跡は姉、舞のものである。 舞は今京都にて芸妓をしているのだからから。まず金銭的に逼迫して強迫されて書かれたとはまず考えられない。さて、果たしてどういった内容であるのだろうか。 --------------------------- ぐうたら男へ 京は晩秋の紅葉が色濃く道道を散り、すっかり冬が近づいて来るようになりました。 こちらは相変わらず元気に過ごしています。 ただ、お前が長崎に行ってしまったので母と姉に手紙を書いても持っていってくれる人も、読んで上げる人も居なくなってしまい、その点だけは不自由するようになってしまいましたが、それは、それ。運が良ければ、誰かが読んでくれるだろう。と割り切って、人づたいに手紙だけは定期的に送るようにしています。 お前も季節毎位には手紙を出してくれているのでしょうね、出していなければこの手紙を機に、是非書いて上げて下さい で、用件というのは実はとっても簡単なのさ。 あたしが贔屓にしてもらっている江戸の呉服屋の旦さんが、今年の春先から急に床につくようになってしまったというんだよ。今までは舞妓を今年はやれ五人、いや六人は水揚げするぞ、と暇さえあれば祇園に通っていたお人がだよ。 おかみさんの話では結婚以来、こんな事は一度もなかったと言うし、最近全くご無沙汰なのでどうしたのか?と芸舞妓通し話をしていたら、ばったりと旦那さんが京に囲っている芸妓にお手当を持ってきた女将さんと会って、ふとお前の事が話に出たんや。 たまたま偶然。身内に蘭学医がいるんや。と言うお話をしたら、 「漢方ではなくて蘭学で治療したら良くなるやもしれませんね」 と是非是非紹介をと強く言う物で、この手紙を書いています。断る断らないはお前の自由。とりあえずそう言う事だから、 姉 舞 京都にて 追記 呉服屋の旦那さんは江戸で五本の指に入るお金持ち。金払いも良し」 --------------------------- 流石一流の芸妓はお金に関しては鼻が良く効く。 黙読を続ける朱がねを着物の雨を振り払う事無く聞き入る女。おそらくは間違いなくこの女はその旦那の妻ではなく、使い走りの用人なのであろう。側で見ると良く分かる。肌には金持ち特有の婉然とした艶が無い。 「こちらは、柏屋の次男、二郎様です。長崎に行くと言いましたらついていくと聞かないので連れて参りました。私は二郎様の乳母にあたります」 「なるほど。事情は分かった。それで旦那さんの症状はどうなんだい。漢方医は何と言っているんだい」 「腫瘍では無いかと。内臓にできものが出来たのでは無いかと言うのですが、でも、食欲はありますし、その見立て違うんではないかというお医者さんもいらっしゃいますし、結局何やら良く分からず、腫瘍に効くという薬を飲んではおるのですが、全く良くなる気配はありません」 「症状は?」 「寝ている事が多くなりまして、あまり動き回らなくなったせいか脚がむくむようになって、毎日髪からだけでなく、全身から毛が抜けてきています。食欲も少なくなりましたし、食べても下痢をする事がしばしば……これだけで先生何か分かりますか?」 「砒素中毒」 「砒素」 江戸時代。砒素は鼠殺しとして家庭の中にも入ってきていた。毒性については言うまでも無い。無味無臭のこの薬品は大量に飲ませれば毒の形跡無く相手を殺すことが出来、少量飲ませれば相手を死の淵に追いやる事無く、苦しませる事が可能となる。 「症状は似ているかもしれない。その顔ではそう指摘した医者も居たようだな」 「その通りでございます。流石のご慧眼です。しかし探せど探せど毒が見つからないのです」 「見つからない?」 興味をそそられたのか、ただ単純に報酬に目がくらんだのか、朱がねは翌日には簡単に荷物をまとめ江戸へと旅だった。この時代の主たる移動手段は徒歩又は馬である。 人の生き死に関わる急ぎの用ということもあり、朱がねは用意された馬に乗り、数々の宿場町を一気に駆け抜けた。関所では往来手形を見せ、すぐにも用意された新しい馬に乗り換え、走り続ける。朱がねを先導したのは意外にも、始めて会ったときは情けなく小さく縮こまっていた二郎であった。聞けば年は既に十四歳。立派な大人なのである。 「もっと年を取っているかと思ったが、ある意味子供連れである方が、宿場町で悪さをする気にならないから、伝達者としては適切な判断であったかもしれない」 「子供扱いしないで下さい」 むきになる所が子供の証である。 「女の柔肌を知っているのかい?宿場ごとにはそりゃ綺麗な女郎が居て楽しませてくれるのに、お前の生で勿体ないと言ったらありゃしない」 「……」 「おぼっちゃまをからかって悪かったな。じゃ行くぞ」 乳母は長崎に残り、朱がねの家の留守番をする事となった。長崎を経ってはや七日。交通手段が未発達の時代としては恐ろしく早い速度で江戸の町へ到着した。ひときわ広い屋敷の表門に二郎は馬をつける。それを見た門番が慌てて檜で出来た熱い門戸を開く。 「御開門」 ぎいいと音を立てて門が開く。朱がねも二郎に倣い、馬を下り、手綱を引いて門の中に入った。途中門人が馬の手綱を預けるように促してきたので、黙ってそのまま渡すことにした。もとより自分の馬では無い。特にこだわる必要は無いだろう。 「今日はとりあえずお休みになりますか?それとも父に会っておきますか?」 「その為に来たんだから、会っておきたいね」 汚れた足を玄関で綺麗に洗い流して貰う。足袋も足も泥だらけである。濡れた手拭いを受け取り顔と腕の汚れも忘れず綺麗に拭き取る。白い手拭いが見事に黒く染まって行く。顔をちょっとふき取るだけで、疲れがあっという間に吹き飛んで行くような気がするのは気のせいであろうか。足を洗い流して貰っている間に茶色い漆の塗られた鎌倉彫のお盆にのせられて香りの良い緑茶が運ばれてきた。今の季節、新茶ではあるまいが、これは良い臭いがする。 「中国渡りのお茶です。竜神茶と言うそうです。では行きましょうか」 「おう」 促されるまま、広い木の廊下を歩いて行く。びた、びたという足の音が不必要に廊下中に響き渡る。この音の反響具合では相当奥まで広い廊下である。大概主人の部屋というのは家の奥に作られる物だというが、この家もそうした習慣を踏襲している様である。先走りが出たのか、鶴の蒔絵の付いた引き戸の前には既に一人の女性が座り、二郎と朱がねの到着を待っていた。 「二郎。おかえり。ごくろうさまでした。お父さんがお待ちです」 「はい、母上もごくろうさまでした」 看病の色が残る色白の面立ち。症状は良くなっていないのであろうか…… 「わざわざ長崎からありがとうございます。主人は今起きております。どうぞ宜しくお願い致します。先生だけが頼りです」 「お、おう」 二郎の母は既に涙を浮かべていた。もう何を頼って良いのか分からない。少々精神が混濁した状況なのであろう。重い戸を座って開いた中は畳が引かれている。中は想像していたよりもそれ程広くは無い。八畳程であろうか。火鉢がいくつか焚かれているせいか、廊下よりも中は寒くは無い。白い蒲団の上には体を半分起こしているこの屋敷の主人と見られる男が右腕を体の後ろの支えにして座っていた。隣には何やら病人には不釣り合いの華やかな顔つきの女性が控えていた。綺麗に結われた髪に身に纏うのは江戸で流行の振り袖である。花柳界の女性、そして主人の妾の一人であることが簡単に想像が出来た。 主人の頬はこけ、髪は白髪となり抜けてきているが、眼孔だけは衰える事無く鋭く光っている。元気な頃はおそらく目の利くそれは優秀な商人であったのであろう。 「この様態なので、蒲団に入ったままで失礼する。二郎ご苦労だった。もう下がっていいぞ」 「はい」 会釈をして、二郎はそのまま部屋を立ち去った。親子とは言えそっけない物である。 「先生の名前は”朱がね”というのだそうだが、珍しい名前であると思うが、長崎ではそうでも無いのかね」 「私の父が丹を取る山師でして、その辺からこの名前がついたようです」 「そうですか。では少々見て頂けますか」 「お任せ下さい」 朱がねの目つきが変わる。ここからは専門分野である。側に寄り、こけた腕を取り、口の内部を確認する。舌が白くなり、黴が溜まっている。枕には脱毛が激しい。内蔵系の疾患という見立ても決して悪くは無いが、やはり毒物系の何かを盛られている可能性を否定できない。 「大体分かりました。とりあえずご主人の一日の行動を見させて頂きます。診療はそれからと言うことで」 「と、言うことは?」 「内蔵系の疾患の可能性は漢方医に任せて、私は悪まで毒物系の疾患の可能性を考えて動きたいと思います。まず毒がどこから来ているのか、来ていないのか判断しないと」 「まさか!先生の今の言い方では私にはまだ毎日毒が盛られているとでも言いたげな口調では無いですか」 「その可能性は高いです。容態が常に一定。良くもならず悪くもならず。これは毒を盛られている人間の症状に一致します。個人的に毒の元は砒素ではないかと」 「砒素、確かにそう言った医者も前に居たが」 「毒殺というとまず砒素が浮かぶのはおそらく私だけでは無いでしょう。次に浮かぶのが鉛中毒、そして青酸などの致死系の毒薬です。ご主人の意識はしっかりしていらっしゃる事からも後者二つの毒を使用された可能性は低いと思います」 「鉛を使われると、具体的にはどうなるのだ?」 「頭がぼうっとしてきます。語気もふらふらとしますし。意識が混濁する事も御座います。もしご主人が晩酌に舶来渡りのお酒などを飲まれていた場合はその可能性が高いですがどうでしょう?」 「舶来渡りの酒など元々飲まない。床についてからは大好きな日本の酒すら口にはしていない」 語気が荒れ、脈も荒れてきた。今日の診断はここまでが限界だろう。朱がねは乱れていた蒲団の端を元に戻し、一礼し部屋を後にした。部屋を出てすぐの場所に二郎が立っているのが見える。ぞんざいに扱われてもやはり肉親の危機というのは気になる物であるらしい。 「先生どうでしたか?」 「ああ、見てきた。出来ればでいいのだが、この部屋から一番近い部屋を借りられたら嬉しいのだが」 「どうしてですか?」 朱がねはそれ以上答えなかった。 毒を盛っている人間が居るとするのであれば、柏屋の主人が死亡した場合一番得する人間がその人物に間違いないだろう。 「先生どうしました?」 「あ、すまん。大分疲れたようだ。今日は休んでいいか?」 「はい。ではご希望通りの部屋を用意致します」 「この家にお前の兄弟は何人居るのだ」 突然の質問に二郎はふっと歩を止めた。それが今回の事件とどう関係があるのかといった風情である。 「いや、別に言いたくなければ良いのだが、ずいぶん冷たい親子関係だと思ってな」 「私には兄が居ます。今大阪で商いの勉強をしていますが、後は妹が三人程居ますがまだまだ小さくて数に入るかどうか」 「そうか、やはりどこの家も長男だけ大切にされるのだな。お前も若いながら苦労が多いだろう」 「そうでもありませんよ。お陰で好きに勉強を続けられますから。将来的には先生のように蘭学医になりたいと思っています」 「蘭学医にかい。やめとけよ金ばかりかかって儲からないぜ」 「そうですか、私は面白そうだなと思いますが 後は母の他に見ての通り父の妾が一人居ます。二年程前からこの屋敷に住み着きお部屋様として主に父の面倒を見ています。年齢的にはまだ二十歳程でしょうか」 「なる程な。妾としては主人に死なれてはこの家に居る理由も無くなるから、看護にも必死なのだろう。大体の人間関係は分かった。ありがとうよ」 二郎は廊下を歩き続け、朱がねを部屋へと案内した。 用意された部屋は六畳程の和室であった。洗い立ての浴衣を着てごろんと転がる。部屋の隅には既に火鉢が用意されており、十分に温められた部屋から冬の冷気を感じる事は無い。 「明日様子を見て、血を採らせて貰うことにしよう」 今後の大体の方針が決まり、朱がねは早々と床についた。元々悩むのはあまり好きな方ではないのだ。 「報酬はどうなるのだろ。明日聞いてみるか」 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 朝 朱がねは部屋に運ばれた膳を食べる前に、主人の部屋へと向かった。主人の部屋はまだ起きていないのか部屋の中を覗いてみても、まだ暗いままである。慌てて下女が膳を持って朱がねを追いかけて来る。とりあえず廊下で運ばれ来た膳の中のみそ汁を軽くずずずとすする。 「持久戦だな」 二刻ほど過ぎてから、主人は起き出してきた。手水を使い、お粥を蒲団に入ったまま口に運ぶ。主人の口に入れる物は全て事前に朱がねは少量取り、小分けにしておくことにした。水、粥、午後は小豆汁である。午後の体調の良さそうな時間帯を見つけて、体内の血を左腕の静脈から採取する。基本的には瀉血と同じ要領で血を抜き、傷口を頭より上に上げて血を止める。主人はこうした蘭学の手法を使った血液の採取は始めてであるらしく、腕の筋肉を殊の外緊張させ、口をへの字に閉じて痛みを堪えていた。 「緊張させしなければ、さほど痛い事はありません」 「儂が口にする物全ては毒味が済んで居る。今更毒の検査などは意味が無いと思うが」 「念の為です。砒素の場合、微量であれば発症の可能性が非常に低い為、毒味だけによる検査では不十分なのです」 「毒味以外に検査する方法があるとでも言うのか」 「あります。蘭学にはその方法があります」 朱がねの診察が終わった後、日課となっているらしい回診が漢方医によって行われた。訪れた漢方医や屋敷の者達は朱がねの行動を不審がったが、主人を完治させる為である。多少の奇行は目をつぶるべきだろう。元々この時代医者に免許などは存在しない。自分自身が”私は医者だ”と言った瞬間から医者になれるのである。だからこそ医者は腕が常に問われる事になる。資格が無いからこそ、医者に対する評価は患者を直した数でしか評価する事が出来ないのである。 あっという間に一日が終わり、主人が蒲団に寝付いたのを確認してから朱がねは部屋へと戻った。 「血液から、まず検査して行く事にするか」 砒素は古来無味無臭。殺人の調整が簡単であった為、”賢者の毒薬”とあらゆる所で利用されてきたが、砒素の検出方法が確立されてからは、体内への残留日数が多い事からも”愚者の毒薬”へと名前を変えた。 持ってきた荷物を紐解き、まず血液に、亜鉛と薄い硫酸を加え、硝子で作った容器の中に入れる。砒素があれば、水素と砒素が化合して水素化砒素が発生する。水素化砒素は熱で分解されるため、硝子管に通しながら加熱をすると硝子管内に砒素が顕れる。これを砒素鏡というが、この砒素鏡が出来るか否かで、砒素の有無・含有量を求めることが出来る。 朱がねは生成された結晶を最新鋭の顕微鏡で覗き込んだ。牛革製のケースに小さな硝子の付いた持ち運び可能な小さな器具ではあるが、現在の日本では所持している人はそう多くは無い。例え居たとしても現場で使用してしているのはおそらく朱がね一人であろう。 「やはり出ている。三酸化砒素か」 夜を徹して残りの対象物を検査する。しかし主人の言う通り、血液以外の対象物からは砒素を検出することがどうしても出来なかった。対象物の数が減るにつれて朱がねは焦りつつあった。これでは原因が分からない! 「運が良いのもここまでか」 その日は寝るのを諦め、砒素の対処薬を処方した。砒素は体内にたまりやすい為、とにかく体内の蓄積された毒を外に出すことが先決である。そう考えるとまず塩類下剤の投与が有効である。長崎において、砒素では無いかという大まかな当たりを付けていたので、この程度までの薬品は持参してきたのである。 日の光が部屋に届いてくる。夜が明けてきた様である。 (◎o◎)(◎o◎)(◎o◎) 「砒素が出たと」 「必要であれば、番所に届けるよう書類を作成します。しかし摂取原因は不明です」 「それで、、、直るのか?」 「薬を処方致しました。すぐには良くなりませんが、体内の砒素が徐々に体の外に出るに連れ良くなってくるはずです。問題は原因です」 「先生は二日前おっしゃった。薬を毎日飲まされている可能性がある。と」 「様子を見るしかありませんが、とりあえず口にされている物からは検出されませんでした。今後も注意は必要です」 「口以外から摂取している可能性がある、とはどういう事だ」 「今日はご主人が来ている浴衣、蒲団も全て検査させて頂きます。それらに毒薬を染み込ませて皮膚越しに毒薬を摂取させられている可能性があるからです」 「皮膚越しにだと。そんな事が出来るのか!」 「皮膚が腫れたりした時に軟膏を塗ることがあるかと思います。軟膏の膏薬は皮膚に染み込み、原因を駆逐します。それと同じ原理です。 おそらく犯人は毒物に詳しい、知識のある人物であると考えられます」 主人は呆然とした顔つきのまま固まっていた。側にいた妾の手を借り、浴衣、褌、蒲団など全てを新しい物に交換し、古い物を全て朱がねの部屋へと運んだ。気のせいか、妾の手は冷たくなり、表情は青ざめて来ている。 「すまねえな。扇を持つ人間に力仕事をさせてしまって、犯人がどこに居るか分からない以上、とにかく作業は早急にしないといけないのでな」 「は、いえ、大丈夫です」 誰にも触れないよう部屋に封をし、朱がねは部屋の中へと入った。何としても感染源を探し出さなければならない。蒲団の微妙な染みなどを一つづつ切り取り、水に付けるという抽出作業を繰り返す。 「どれだ、頼むから出てくれ!」 結果が出たのは深夜であった。朱がねは証拠の品を手に持ち、主人の部屋へと向かった。まさかこんな物に毒が染み込ませてあったなど誰が考えついたであろうか。考えてみれば普通の人であればほぼ毎日、病人でも一週間に一度は交換する品である。定期的に対象者が新しい毒の付いた品を常に身につけてくれる。考えた人間は相当頭が良いと考えて良いだろう。 「ご主人。結果が……」 返事は返ってこなかった。見張りをしていた人間が蝋燭の火を付け、主人を起こす。声をかけ、頬を叩くが起きない。眠っているように 「朱がね様。死んでいます!」 「殺されたか。家人を全て起こせ!奥方に報告を!」 静寂が破られ、大騒ぎが始まった。同心が屋敷内に入って検分するが、遺体は全く汚れておらず、安らかな死に顔からは病死であるとしか思えない。朱がねは事情を説明し、手に持っていた褌を同心へと渡した。 「これに、舶来渡りの化粧水アクア・トファナが染み込まれていた。」 「何!何だそれは」 「和蘭船で見たことがある。女性の美容には効果がある化粧水だが、こいついには砒素が含まれていて暗殺に使うことも出来る」 「同心!妾が死んでいます。自殺であるようです。机に遺書が!」 朱がねと同心が声のあった場所に駆け込むと、天井に綱が吊され、柏屋の妾の一人が首を吊って死んでいる姿が見えた。机の上には紫色のガラス瓶が置かれ、その下にはたどたどしい平仮名で 「ごめいわくをおかけしました。ごしゅじんさまといっしょにいきます」 と書かれていた。朱がねは冷静に吊された死体を観察している。既に長崎で数十体の腑分けを経験した朱がねであるから、死体が別段珍しいからでは無い。死体から目は飛び出、下半身からはぽたぽたと小水らしき液体が漏れている。同心は手人に妾を釣りから降ろすように指示をし、主人の遺体の元へと戻った。安らかな死、同心が出した結論はこうだった。 「妾単独犯による怨恨による殺人事件である」 元々江戸は安全な町なのである。時代的の様にまず頻繁に事件などは発生しないのである。 江戸全体で同心は十二人しか存在しない。その理由は刑罰が非常に重かった事が一つ上げられる。放火してその家で死人が出なくても、火がついただけで死罪である。掏摸は三回までは入れ墨を入れられるだけだが、四回目は金額の如何に関わらず死罪。泥棒も十両以上を盗めばその場で死罪となる。とにかくちょっとした事で死罪になるのだからたまらない。誰しも自然と罪を犯してまで何かをしようとはまず考えない物なのである。 朱がねは様子を見守りながら、再び妾の部屋へと戻った。既に遺体は釣りから降ろされ、白い布がかけられている。元が美人であった為、無惨である。そうした朱がねの姿を見て、次男の二郎は後ろから声をかけてきた。 「先生、折角来ていただいたのにこの様な事になり申し訳ありません。お礼は十分に致します。先生が検証を始めた為に妾も動揺したのでしょう。結果として犯人は父を道連れにして自殺してしまいましたが、これは先生と関係ありません。ありがとうございました」 「犯人が自殺?」 朱がねは何を馬鹿なことを、と言いたげな顔をして二郎の耳元に口を近づけた。 「犯人はどう考えてもお前だろ。まあいいや。俺はもう長崎へ帰る」 「何を馬鹿なことを……」 二郎が後ろを振り返ったが、既に朱がねの姿は無かった。慌てて廊下を追い、何か声をかけようとしたが、二郎の声は出なかった。朱がねの背中からはもう何も言うつもりが無いということが伝わって来ていた。ではもう余計な事は言うまい。父殺しの罪は当然死罪である。証拠は何も無い。同心も他の人間も全て妾の犯罪として納得したでは無いか。 「あのような田舎者をまともに取り合う者など……」 翌朝、朱がねは早々に柏屋を発った。受け取った報酬は百両であった。平民の家族が一ヶ月二両で暮らせる時代に、これは破格の金額である。 帰りはゆっくりと宿場町を寄って帰ろうか。朱がねは懐も温かいし、今度は急ぐ必要も無いのでのんびりと歩きながら宿場町を一つづつ長崎に向かって進んで行った。 「何故分かったんです」 箱根の関所で馬に乗った二郎が追いついて来た。葬式が終わったとたん、どうしても気になって追いかけてきたのだと言う。一目がある所で話す話題では無い為一応席を立ち、人の居ない空地へと向かう。朱がねは腰に下げた瓢箪を二郎へ投げて渡す。素面で話す話では無いと言う事と腰に差した脇差しを見せる為である。いざとなれば刺す。そういった意気込みが二郎には伝わってきた。 「もう一度聞きます。どうして分かったんです」 「まず妾の死に方がおかしい。首を吊った死体はあんなに綺麗じゃ無い。実際に見たことあるかい。酷いもんさ。月のものから、小水、大きい方までダラダラ流れて汚らしいったらありゃしない。ありゃ一度殺してから吊した死体だよ」 「でも死体はもう無い。証拠なんて何も無いじゃないですか」 「そして主人の死だ。アクア・トファナは致死性の毒では無い。相当量一度に飲ませないと死ぬような事はまず無いのだ。元々女性の化粧品として開発された物だからな。妾の部屋からはアクア・トファナ以外の毒は見つからなかった。それはどう考えてもおかしいのじゃないか」 「……。何故犯人は私だと」 「消去方法で消していけば分かる。毒に詳しく、俺が砒素を検出した事を知っていた人物。妾には毎日単純に毒を褌に染み込ませる位のことは出来たかもしれないが、毒薬の細かい処方によって、人を殺す事などかけてもいい。絶対に出来ない。毒は処方を間違えると恐ろしい形相で死ぬことになるからな。あの死に顔から察するに、俺には出来るだけ苦しませたく無い、という毒殺師の気持ちが見えた お前は毒に魅入られた人間だ」 「毒に魅入られている人間」 「次は俺が聞く番だ。何故父親を殺そうとした。実の父だろう」 「……」 「黙っている事は無いだろう。たとえば、の話だ。たとえば」 「父の妾のあやと恋仲になっていた。最初は興味本位で居たのだが、気が付くと腹には子供が……父が京都に出張していた時の子供なので計算が合わなくなってしまう。それで」 「計算上の問題か。それで発覚を恐れて妾を殺したと」 「あの夜。妾が突然俺の部屋にやって来て騒ぎ始めたんだ。もうおしまいだ。これで私たちは市中引き回しの上一番屈辱的な形で殺されてしまう、と。妾はその屈辱には耐えられないだろう。であれば、二人とも一番幸せな状態で殺してしまえばと思った」 「思った通りの成果は出たのか」 「あやの分量は少々間違えた。茶に毒薬を入れ飲ませたのだが、量が少なくて苦しみ始めてしまったのだ。それで手で首を絞めて殺した上で吊した。そのお陰で父の分量は間違えなかった。元々父の体は弱っていたし、唇に筆を使って毒を垂らすとそのまま眠るように逝ってしまった。 元々父は砒素で体を弱らせて、病死に見せかけるつもりであったから、たまたま最後の筋書きが変わっただけで、特に問題は無い」 「そうか。毒を使って人の人生を動かす快感。お前は感じなかったか」 「え」 朱がねの一言に二郎は体を動かして反応した。 「何度も何度も毒薬を調合している間にお前はその快感を忘れられなくなっていかなかったか、病死に見せかけたかったと言ったが、何故毒を使って一気に殺そうとしなかったのだ。理由は簡単だ。お前は意識しない間に、毒を扱う事を楽しんでいたのだよ。 あと一滴入れたらどういう症状になるのだろうか、想像してその喜びに打ち震える事は無かったか、絶対に無かったとは言わせない」 「そんな事はあり得ない」 「自分の気持ちに正直になれ、でなければあれ程綺麗な死に顔を出せないはずだ」 「あり得ない」 「本当に、ここ数ヶ月今まで感じた事の無い快感を、生きる喜びを感じる事は無かったのか」 朱がねは瓢箪の中の酒を軽く煽った。十四の子供が自分の不倫を隠すために父親を恋人もろとも殺してしまう。頭の中では分かっていても、正直に言えば浴びる程に酒でも飲まなければいられない気分であった。 「ま、俺も偉そうに説教できる立場では無い。是非道を究め良い毒殺師になってくれ」 「もう人は殺す様な事は絶対に致しません。これが最初で最後です。僕は立派な蘭学医になります」 「そうであることを祈っているよ。お前のお陰で俺は姉に良い帯を贈ってやれそうだ。ま、たまには姉さん孝行しないとな。又会った時に何言われるか分からないから」 朱がねは瓢箪を腰にくくりつけ、二郎を後に馬の方へと向かった。そして最後にこう付け加えたかったが、思うだけでそれ以上会話を続けようとはしなかった。 「俺も父を殺した事がある。そう気にする事じゃ無い」 因果応報。輪が回る。 走り去る朱がねを二郎は見送った。数年後、二郎は朱がねに師事すべく長崎へと再び舞い戻る事になるが、それは大分先の、まだ変わるかも知れない未来の話である。 |
| コ |
