

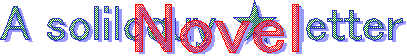
| お気楽犬生・一二三(ポメラニアン) 「こんにちは!」 とばかり玄関に小さな黒い犬が座っていた。 普通の人間であれば、動揺する所であろうが、近所でも動物屋敷として有名な亜美の家としてはこれは普通の出来事であった。迷子の犬、鳥が居ると、皆とりあえず亜美の家へと連れてくる。連れてこられた犬や鳥は近所の動物事情を誰よりも良く知る亜美の手によって、それぞれの家へ帰されたり、時によっては保健所へ連絡を取り買い主を捜す事となる。 「一週間前は確かカルガモの赤ちゃんだったけど、今日はポメラニアン?」 玄関の戸を開け、ポメラニアンを中に入れる。体重は大体一.五キロほどであろうか。小さく綺麗にまとまっており、骨格も悪くは無いが、相当迷子になっていたらしく、毛並みはボサボサで一度シャワーを浴びさせないととんでもない状態になってしまっていた。この犬はどう見ても近所に住んでいる犬では無い。明らかに違う犬である。 「えっと、首輪はしてない。お名前は?と聞いて答える訳は無いか。分かった。私に任せておきなさい」 庭の外でシャワーに入れ、段ボールの中にポメラニアンを入れる。ポメラニアンは愛玩犬である。迷子になれば迷子になりっぱなしで、新しい買い主にあっという間に懐いてしまう。保健所に連絡を取り、ポメラニアンの迷子が出ていないか確認するが、現在迷子は出ていない様である。亜美の家には既に先住民として雑種の犬が住んでいたが、ポメラニアンはニコニコ・ニコニコ。全く気にする素振りは無い。 「保健所には連絡無し、か。とりあえず保健所にはあんたが家に居ることは登録しておいたから、買い主が来るまでゆっくりしていなさい。保健所に連れて行くとね、一週間で殺されてしまうのよ」 最近はテレビでもそうした犬産業の”タブー”の部分を見せるようになってきた。全部で七つの部屋があり、一日ごとに柵が開かれ、部屋を移って行く。最後の七つめの部屋にたどり着いた時もし買い主が現れなければ、そのまま殺されてしまう事になる。最後の七つ目の部屋に来たとき、犬たちは教えていないのに危機を感じるそうである。その部屋に入った犬はどんなに愛想の悪い犬であっても、自分の得意な技や飼い主が喜んだ出あろう技を部屋に入ってくる人に対して繰り返すのだと言う。それが無駄な努力と知りつつも、である。 亜美の家はそうした犬の危機を少しでも救う為、ボランティアとして買い主が見つかるまでの一定時期、保健所に通知を行った後、家で犬を預かるようにしていたのだった。 愛らしい黒い目に小さな口。こんなに可愛い犬を殺させる訳にはいかない。亜美は夜遅くまで新築の家を建てている家から貰った余り物のタル木を使って小さな檻を造った。 本来は家の中で飼う犬であろうが、そうした習慣の無い亜美の家では外にこうして檻を作ってあげる事しか出来ない。ポメラニアンは亜美の指示に従い、今まで何匹かの犬が使用してきた小屋に潜り込む。本来ならリードで縛っておくべきなのであろうが、小型犬であるため檻の中に入れるだけで十分であろう。 「名前、付けないとね。うーん色が黒いからクロにしようか」 返事はない。大分放浪していたのか、かなり疲れてしまっているようである。亜美の家に隣はない。四方八方田圃のみである。とりあえず田圃のあぜに落ちたり、水が増えてきている用水路に落ちなくて良かったと考えるべきであろうか。 とりあえず、今の季節は夏であるから、外で寝ても凍死する事は無いだろう。気にはなりつつも、亜美はそのまま家へと戻った。 一週間経っても、二週間経っても飼い主は現れなかった。ポメラニアンの毛色は茶色が普通であり、その次に多いのが白、黒は滅多に生まれない。色がちょっと違うだけで犬の値段は大幅に変わってくる。鼻の色、肉球の色、耳の角度も重要な要素である。クロは毛並み、体型、骨格、どこを見ても最高級の部類に入るショードッグ系のポメラニアンである。 「飼い主も絶対に探していると思うんだけど」 側によると甘えてきて、何とか家の中に入ろうとする。家に犬を上げるという習慣の無い亜美は悩んだ。うるうると涙を浮かべそうな目で亜美に必死にアピールするクロ。これは困ってしまった。 「じゃ、せめて段ボールの中に入っているんなら考えてもいいけど」 玄関先に置いてあったスーパーで貰ってきた段ボールを差し出すと、クロは亜美の言う事を理解したらしく、大人しく箱の中に入って行った。 設置場所は台所に決まった。ひょこっと顔を出しては、ちょこちょこっと夕食の準備の間に出るオヤツを頂く。本来であれば、ソファーの上などにゴロゴロしたいのだろうけど、早々そう言う訳にもいかないのだ。 夕食が終わり、夜の時間となるとクロは無理矢理外の小屋に戻される。怒るのかな?とも思ったが以外と素直に小屋へと戻る。育てた飼い主が優しい人であったのか、性格は至って温厚である。 亜美は後ろ髪を引かれつつも、まだ生温かい段ボールを抱えて家へと戻った。 そんなノンビリとした日々が続いたある朝。 いつも通り段ボールを持ってクロを迎えに行くと、そこにはクロの姿は無かった。 脱走?まずそう思ったが、クロの脚力では一メートルはある柵を越えることは出来ない。当然太いタル木を使っているから、破壊も不可能である。 慌てて近所を走り回るがどこにも見つからない。どこへ行った。どこへ行った。しかし、待てど暮らせどクロが二度と亜美の家へと戻ってくる事は無かった。 「クロ?田圃で遭難してしまった??」 仕方なく保健所にクロが逃げ出してしまった事を連絡する。これでクロとの最後の縁が切れた・・・そう思った矢先、亜美の元に不審な電話がかかってきた。 「おう。この泥棒野郎!聞いてるのか」 「え?どちら様ですか」 「そんな事はどうでもいい。良くも俺の大切な犬を盗んでくれたな」 クロだクロの事だ。亜美は電話を力強く握りしめた。 「ポメラニアンの事ですよね。迷子になってたんですよ。保健所にも登録してました。何か勘違いされていませんか?どうやってクロを連れていったんです?」 「登録してた?そんな事は知らないが、夜中に連れに行ったのよ。お宅らが素直に渡すとは思わなかったから、そうしてやったのさ!」 「私はクロを預かっていたんです。迎えに来て頂ければいつでもお渡ししました。保健所にそのまま置いていたら一週間で殺されていたんですよ!」 「そんなこと知らねえよ。うるせえよ、泥棒」 電話は無情にも切れた。 犬が迷子になったら保健所に連絡して、迷子犬登録をする。たったこれだけの事を知らない人が可愛い犬を飼って良い物だろうか。 亜美は再び保健所に連絡し、事情を話して迷子ではなく元の飼い主にクロが戻った事を連絡した。亜美の落胆した声に保健所の人はふとこんな事を言った。 「今こちらにペットホテルに置き去りにされたポメラニアンとチワワが居るのですが、もしご迷惑でなければそちらで預かって頂けませんか?」 「置き去りにされた犬、ですか」 「元の飼い主が、最初にお金を払ってその後指定の期日に迎えに来なかったそうなのです。 こうした場合やはり規則通りですと一週間で処分と言うことになるのですが、何しろ血統の良い犬ですので、もしそちらでそう言う事情があるのでしたら、ご検討して頂けると幸いなのですが」 「はい。後日又ご連絡致します」 可愛い自分の相棒をペットホテルに置き去りにしたと言う話を聞き、亜美の母は直ぐに引き取る事を決断した。 翌日早速に犬を受け取りに行く。そこに居たのはアルビノであるかと思わせるような白い毛並みのポメラニアンと、それと対照的に殆ど毛の無い茶色いチワワの姿があった。 二匹とも相当怯えている。ポメラニアンは誰にでも懐くタイプの犬種であるが、チワワは違う。飼い主に忠実な、なかなか懐かないタイプの賢い犬である。その犬が始めて会った人間にすり寄り、何かを訴えている。精神的に大分追いつめられているようである。これは放っておくわけにはいかない。 「では二匹とも連れて帰ります」 「二匹共ですか、それはありがとうございます」 帰宅後にポメラニアンはクロの住んでいた家に、チワワはプラスチックで作られた犬小屋へと入る。 昔は犬小屋というと木製の重い物が主流であったが、最近は軽いプラスチック素材の小屋の下側に砂の重りを入れ、簡単に使用する事が出来る犬小屋がかなりの数出回っている。当然の事ながら木製のものよりも、プラスチック製の方が断然値段は安い。 「名前はどうしようか、二匹ペアだからルルとペペにしようか」 かくしてポメラニアンの名前はルル。チワワの名前はペペとなった。 先住者のクロと同じくルルも家に入りたがる。亜美は慣れた手つきで薄汚れた段ボールにルルを入れ、家の中へと運ぶ。チワワも家の中に入りたい様なのだが、どちらかというと小心者の性格なので言い出すことが出来ない。我が道を行くポメラニアンとは全く別の性格なのである。 家の中に入ったとたん、ルルは段ボールから外に出ようとした。こんな窮屈な所に入っていられないといった調子であるが、出たとたんに亜美は手を振り上げて怒った。「ぺんちんだよ。出ちゃ駄目」どうやらルルは”怒られる”と言うことが良く分からないらしい。何度も何度も段ボールの中に入れて、出てはいけない事を教える。 「クロは賢かったのに」 去っていってしまった犬を振り返ってばかり居てはいけない。 ルルとぺぺが住み着く前に、亜美の家ではやはり迷子でやって来た雑種の犬が居た。ペペは毎日その犬と散歩をする事になったのだが、ルルは全く散歩に行かない。毎日ちょっと庭を歩き回るのが唯一の運動である。 ポメラニアンは骨格が弱い為、無理矢理散歩に連れていったりすると、すぐに骨折してしまう危険性があるので無理は出来ない。 ルル自身も散歩は嫌いらしく、仕方なく亜美は自転車の前のカゴにルルを入れ散歩に出かける事にした。川縁を流れる風が気持ち良い。しかしルルはあまり喜んでは居ない様であった。 「ルル、自転車でお散歩嫌い?」 嫌いでは無かったらしい。 時折亜美が庭で自転車のパンクを直していると、慌ててルルがやって来てカゴに入って待っている。如何にも「散歩に行くなら付いていってあげてもいいわよ」と言わんばかりの風情である。 「今日はどこにも行かないから、カゴから降りてなさい。危ないから!」 といっても降りずに、自転車の向きが変わりカゴの中から落ちそうになると、何度も態勢を変えカゴの中に居座っている。結局自転車の修理が終わった後はルルの散歩に行く事になるのだが、その時亜美は何故ルルがそうした行動を取るのか全く分からないで居た。 ルルは亜美は勿論の事時折やって来るお客さんや他の犬にまで尻尾を振る。さすがに大型犬のアラスカンマラミュートの毛皮の上で寝ようとした時は亜美も驚いてしまった。 橇犬の毛並みは下手な毛布などよりも厚い。飼い主に甘えようと腹を上に出しても、オオカミ犬であるから普通の犬と違い、びっしりと毛が生えている。これらの毛は敵の腹に対する攻撃から少しでも身を守るための手段であると言われている。 「あんた、噛まれて死んじゃっても文句は言えないよ」 愛想がいい。それがルルの、いやポメラニアンの唯一の芸であった。 季節は冬を迎え、ルルとペペは亜美手作りのセーターを着るようになっていた。ルルは純毛の毛があるのだが、ペペは毛が無い。もう少し「家に入りたい。家に入りたい」とせがむようであれば、家の中に夜の間だけでも入れるようになるのだろうが、ペペは相変わらずの遠慮犬であった。逆にルルはずうずうしいパワーを全開させ、日中も夜も家の中に自分の寝床を確保する事に成功したのである。 しかし、段ボールから出てしまう可能性も高いので、一応廻りを犬のゲージで囲うことにはしたのだが、どうやら夜な夜なゲージを抜け出して家の中を放浪しているようである。ある日亜美が気が付くと、布団の中にルルの姿があった。 「あんた!自分の布団で寝なさいよ!」 本来であれば、これが普通の家犬の飼い方であるのかもしれない。 いつしかゲージは倉庫の奥隅にしまわれ、ルルは自由に家の中を歩き回る事を許可された。犬の毛が家の中を飛び散る。とにかく掃除が大変にはなったが、それはそれで楽しい時間ではあった。 小型犬は寿命が短い。 更に死産したとは言え、ルルはペペの子供を身籠もったりと小さな体に対する負担が大きかった様である。ある日の朝、起きてみるとお風呂場にて口から血を吐き無惨な姿で死んでいるルルの姿が発見された。 「ルル!ルル!」 何かに取り憑かれたような酷い形相である。口から大量に流れ出た黒い血。可哀想なので死因を調べる為に解剖はしなかったが、死に方から察するに、どうやらルルはフィラリアに感染していた様なのである。 フィラリア。それは蚊が犬を刺した際、感染子虫が血管内から心臓内に到達し死に至るという病気である。体外は成虫になる前に薬を飲用して薬殺するのだが、ルルの場合薬を飲む前に既に成虫が体内に成長し、心臓を狙っていた物と推測される。 自分で歩こうとせず、自転車でしか散歩に行こうとしなかった事や、いつもけだるく元気が無かった事などから考えると、ルルは亜美の家にやって来た時には既にフィラリアに感染していたと考えられるのかもしれない。 いつも通り、庭の片隅にルルの体を埋める。うっかりすると他の飼っている鳥たちが不審がって掘り返す可能性があるので、出来るだけ深く穴を掘り、毛の血を綺麗にふき取った後のルルの体を横たえる。小型犬の死は何よりも突然訪れる。亜美は目に浮かんだ涙をふき取りながら、ルルの墓を後にした。 ルルが居なくなってもペペが居る。そして最近飼ったばかりの大型犬アラスカンマラミュートが居る。亜美の家は相変わらず騒がしいのであったが、やはり亜美の母が物寂しさを隠せないでいた。 「やっぱり家の中にもう一匹位犬が居てもいいんじゃないかしら」 「そりゃまあ、小型犬が一匹増えても、あまり関係無いとは思うけど」 母のその後の行動は早かった。知り合いのブリーダーに電話を入れ、子犬が生まれていると言う情報を入手すると、あれよあれよと出かけて行ってしまったのである。数時間後戻ってきた時、母の手には黒いヨークシャーテリアが抱かれていた。 「ポメラニアン買いに行ったんじゃなかったっけ?」 「そうなんだけど。うーん。でもポメラニアンの生まれた子供は雄だったのよ。お母さんどうしても雌犬が欲しくて」 どうやら普通犬は服を着ないため、どうしてもダラリンと例の物が目の前を通過すると恥ずかしいと言うのである。かくして亜美の家へは犬の宝石と呼ばれるヨークシャーテリアがやって来た。折しも時代は皇太子妃雅子様ブームの真っ最中であり、雅子様が飼っていたヨークシャーテリアのショコラが大人気であった。 こうした世間の流行に犬の世界というのは非常に敏感に反応する。シベリアンハスキーが主人公の漫画が流行ればシベリアンハスキーが人気ナンバーワンの犬となり、雅子様のショコラがテレビ画面に向かってニッコリ笑えば、その年の人気ナンバーワンの犬種はヨークシャーテリアとなる。しかし多産な一度に八から十匹の子供を産む中型犬のシベリアンハスキーと違い、ヨークシャーテリアは超小型犬。何とか繁殖させようとしても一度の出産では最大で二匹程度しか産む事が出来ない。 かくしてナンバーワンの座はやはり中型犬のゴールデンレトリバーへ移り、その後は小型犬のミニチュアダックスフンドへと移る事になる。 ヨークシャーテリアは育て方を間違えると、超小型犬から小型犬へとあっという間に変貌する。本来であれば一.五キロから二キロ以内で収まるはずの体型が、餌のやり方や育て方によって五キロまたは十キロ近い体型へとデブデブ体型になってしまうのだ。 これはヨークシャーテリアか?それとも新しく開発された品種なのか?と思ってしまう事も少なくない。元々ヨークシャーテリアはイギリスにおいてペストが流行した際、その感染源である鼠を退治する為に生まれた品種である。超小型犬ながら実際は立派な狩猟犬なのである。であるから骨格もしっかりしているし、脚も早い。餌さえ大量に与えれば他の超小型犬とは違い、大幅に成長してしまう品種なのである。大きく元気に育てば良いではないか、という人も居るかもしれない。しかし百年以上に渡って維持してきたヨークシャーテリア・最適の体型というのがやはり存在するのである。無理な体重増加や体型変化がヨークシャーテリアにとって決して良いことだとはとても思えない。 「名前どうしようか?」 ヨークシャーテリアを見つめる亜美。片手で持ち上げてみると非常に軽い。丁度生まれて百日を経過したばかりなのだという。気になりキッチンの料理用のスケールで体重を量ってみると何と五百グラムしか無い!これは小さな犬である。 「五百グラムって中国語で何て言うの} 「イーチン・バン」 これは一キロの半分と言う意味合いである。かくしてヨークシャーテリアの名前は”イーチン”に決定した。変わった名前。一番困ったのは動物病院の先生である。大概の場合動物のカルテには 名前+号 という方法で名前を記載する。イーチン号、女の子なのにこんな名前で呼んで良いのだろうか・・・これは早めに忠告をして上げた方が 「中国語で発音すると イーチン・ハオ になるね」 ちなみに中国語で”これは何ですか”と聞くと更に危険な単語となる。 先人のポメラニアン達が道を造ってくれたお陰で、イーチンは生まれながらにして家の中を自由に歩き回り、寝る事が許されていた。 トイレとウンチの時だけ庭に出て、終わればあたふたと家の中に戻ってくる。冬場は誰よりも早くコタツの中に入り、夏場は一番涼しい網戸の側で白い腹を出して寝ている。 これはぐうたらな犬がやって来た、と思ったが実際の所頭は悪くない。誰にでも愛嬌を振りまいていたポメラニアンと違い、懐くのは餌をくれる母と、毎夜のコタツ仲間である父だけである。 基本的に亜美の家で飼われている犬たちは父に逆らう様な事はしない。これは犬たちはその家の最高権力者をエースとして認めるという習慣があるからである。大概に置いてその家のエースは犬達の手によって年輩の男性が選ばれる事が多いようである。 このエースが存在しない家庭の犬は傍若無人に暴れまくり、人間よりも偉そうに振る舞う傾向が強い。これは間違い無く人間よりも自分の方が偉い、と勘違いしているのである。 亜美には本当に困った時、母が買い物に行ってしまったり、ちょっとした旅行に行ってしまった時のみ甘えてくるのである。大体そう言う時は亜美は空気で分かる。仕方なさそうに首を傾げて側に寄ってくるイーチン。こんな時しか遊んでくれないなんて、やっぱりちょっとお馬鹿でもポメラニアンの方が良かったのでは無いだろうか、 「昨日ね。近所のペットショップで黒いポメラニアンが売っていたのよ!亜美どうする?買う?」 「え?黒ポメが」 亜美と母は一番最初に飼ったクロの事を忘れてはいなかった。近所のペットショップに通うこと十回以上。最後はペットショップの人間が根負けし、値段を少々負けてくれた。 「イーチン怒るだろうね」 「ま、別の部屋で飼えばいいでしょ」 あまり細かいことを気にしない。訳もなくイーチンは新しい犬を見て怒り狂った。どうも自分のテリトリーを荒らされる、と思ったらしい。うっかり正面きって顔を見せようものなら、噛み殺しかねない勢いである。 「気にしましたねえ。これは困った」 かくしてポメラニアンは別の部屋にて隔離されるようになった。とにかくまだ小さいポメラニアンは元気。誰が来ても元気一杯で甘えて遊び回る。 「お気楽な犬だね」 「それが可愛いんでしょ」 ポメラニアンの名前は丸くてはね回る習性から”キャンディ”と名付けられた。イーチンはキャンディに全く興味が無く、できるだけキャンディとは一緒の部屋に居ないように家の中で移動を繰り返している。後から新しい犬を飼った場合何を気をつけなくてはいけない事は最初に飼った犬をより大切にする事である。イーチンは必ずキャンディよりも先にご飯を貰い、母の腕の中に抱かれて散歩に出かける。キャンディは嫉妬するかと思いきや、結構ノホホンと日々を楽しく過ごしていた。ある日の事である。 「キャンディが居ない」 大学の授業を終え、家に戻ってきた時、家は大騒動になっていた。何と昼間キャンディが庭へ散歩に出たまま帰ってきて居ないというのである。またしても盗まれてしまったのか?冬の日の出来事である。十六時を過ぎた辺りになると、日も大分落ち視界が悪くなってきてしまった。 「保健所には連絡した?」 「連絡した。ポメラニアンの迷子は居ないって」 「そうか・・・」 ポメラニアンは帰巣本能が薄い家犬である。 一度盗まれてしまい家の中で飼われてしまえば、見つける事はほぼ不可能に近い。亜美の頭には一番最初に飼ったクロとの出会いと別れが頭を過ぎった。キャンディとも悲しい別れをしなくてはならなくなってしまうのか。近所周辺はもう五回以上探し回った。足のふくらはぎはもうパンパンに晴れている。居ない・居ない。どこを探しても居ないのである。 「亜美!!!」 家へと戻る道すがら、母の姿が見えた。大きく右手を振っている。見つかったのであろうか?息を切らして家へと戻り、母の元へ駆け寄る。 「キャンディ居たの?無事帰ってきたの、良かったわね」 「・・・。違うのよ。ま、見て貰った方がいいと思うけど、こっち」 見つかったのではないのか?母に促されて、庭の片隅、雑草が生え放題のエリアへと足を進める。母が手に持った懐中電灯を庭の塀の一番隅の方へとあてる、すると暗闇の中にバタバタと何か生き物が居る。 「キャンディ?」 「ひっかかってるの?あんた」 ポメラニアンのふわふわした尻尾に蔓系の植物が絡み、動けない状態である様だ。慌てて蔓を引きちぎり、キャンディ。相当寂しかったらしい。亜美の胸に抱きつき、離れようとはしない。 「何やってるの!心配させて!」 バタバタと汚れた尻尾を上下に振る。かくして安全確保のためにキャンディの尻尾は丸刈りにされ、庭に出た際すぐに戻ってこない場合は即捜索隊が出るようになった。 「キャンディちゃんと戻ってきた?大丈夫?蔓に好かれて無い?」 「大丈夫よ」 部屋の隅の方でキャンディがパタパタと尻尾を振っているのが見える。どうやら今日は無事に庭の散歩から戻ってきた様である。 ポメラニアンの魅力。それはやはり天真爛漫な所であろうか。 いつも気楽にこんにちは。時によっては泥棒にだって笑顔でニッコリ尻尾を振りそうな勢いである。同じ種類ではあっても一匹たりとて同じ犬生は無い。 物語は数年毎に主人公を変え、おそらく、まだまだ続くものと思われます。 ポメラニアン万歳! |
| コ |
